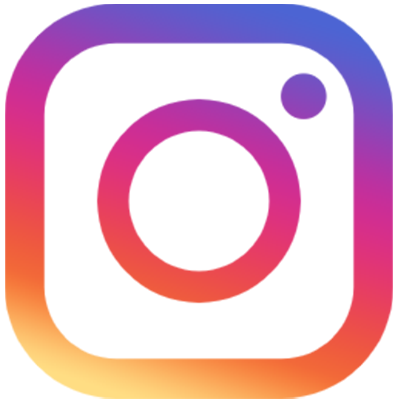毎月23日は小説の日!【託されたラストページ(後編)】
パソコンの前でのにらみ合いが続いていた。
健斗は、ここまで姉と面と向かって話したことが最近あっただろうかと思い返していた。何でもお見通しだと言わんばかりの姉の視線を受けていると、変なことを口走ってしまいそうで怖くなる。
しかし、完成を託された漫画の三十二ページ目が見つからない状況の中ではそうも言ってはいられず、健斗は取っ組み合うように姉の十音の瞳を見つめ続けるのだった。
姉は「最後の原稿のありかが分かる」と告げてきていた。それはつまり「どこにあるのか当ててみろ」という問いかけだったのだ。
健斗には答えを導き出せる「予感」があった。
それでも勇気がなかったので、口には出せずにいた。
そんな健斗の心情を知ってか知らずか、十音は控えめに笑ってみせた。そして、一人言を漏らすようにさりげなく言い放つのである。
「原稿のありかを教えるわ。テレビの横の棚の、一番上。誰かさんが缶詰を入れていなければ」
姉の言うような誰かさん、つまりは担当編集である阿久津はこのところ訪れてはいない。そうなると、十音の告げる場所に何があるかを健斗は知っていた。
カメラから離れて棚を開き、そこにしまわれているものを見た。
「やっぱり、そういうことかよ。三十二ページ目、こんなところにあるのかよ」
「いや、正確には君の心の中にあるんだよ。君はここまで何年も私のアシスタントをやってきた。その中で、どんなものが君の中に残せたのか。漫画家として純粋に興味があるんだ。それに……」
姉の言葉が途切れたのでパソコンの前に戻ると、ビデオ通話のアプリケーションが動作を停止してしまっていた。言葉の途中で切れてしまうと気になるものだ。しかし、すぐさまかけ直してこないということは、これ以上の言葉を期待するなという姉のメッセージなのかもしれない。
ただ、機械音痴の姉だ。
旅に出る前にパソコンを持たせて、何とかビデオ通話ができるところまでレクチャーをしたのだが、不測の事態には対応出来ないのかもしれない。
健斗の瞼の裏には、パソコンの前であたふたする十音が見えてくる。
しかしながら、今はそれを微笑ましく感じている余裕はなかった。
あまりにも重すぎる三十二ページ目が健斗の手の中にあったからである。
彼が持つのは白紙のページ。
すなわち、国民的漫画家である白樺 春が残した最後のページは、「これから誰かが描くであろう空白の一枚」であったからだ。
時刻は午後十時を回っていて、何も胃に入れていないことに気づいた健斗は冷蔵庫のタッパーから白米を取り出してレンジにかけると、冷蔵室を開いて手際よくビニールパックを次々と取り出すと、皿に一つ一つ盛りつけていく。キムチ風味の野菜と豚肉を炒めたもの、それから豚の角煮、加えて粉末状の味噌汁にカットした白菜を投入する。最後に阿久津からの差し入れである桃の缶詰を開けてこれも皿に盛る。
忙しい中でも健斗は食事をしっかりととっていた。流石に原稿が間に合うか間に合わないかという修羅場の時は、簡単なカップ麺やレトルト食品で済ませることはあるが、よほどのことがなければ自分でメニューを考えて炊飯器で米を炊く。
食事に箸をつけて、健斗は目の前の白紙の原稿を睨んでいた。
なるほど、思い返せば生前の白樺はそれとなくこのような状況を想定していたように思えた。
しきりに「原稿は三十二ページある」と述べながら、三十一ページしか描かなかったこと。健斗の仕上げてきた原稿に対して何一つ注文を付けなかったこと。そして、「次に描く時は」という言葉。
それらが導く事実は、健斗の直面する現実と一致していた。
これから彼は『ブルックリン・ブラザーズ』の最後のページを描かなければいけないのだ。
「承知しました。あなたたち姉弟の推理通り、先生のご遺志はそこにあると考えて良さそうですね」
明くる日、健斗は自宅のリビングに袈裟姿の男を迎えていた。頭を丸めてどこか世俗の人間とは一線を画すような心境を抱いていそうな彼は、見たところ疑いなく坊主であったが、実際は無くなった白樺の担当編集である。名を定善といった。
健斗の出した茶をすすってそう述べると、彼は穏やかに笑っていた。
まるで、数日前に担当作家を亡くした編集者の顔色ではない。健斗は彼がやはり本職の坊主なのではないかと考える。
「そ、そうかもしれませんが、無茶が過ぎますよ。それにこっちはあくまで先生の下書きの原稿を仕上げるという仕事を請け負ったんです。それが、一ページだけとはいえ、漫画を一から描くなんて」
健斗は首を振りながら、自分用に淹れた茶の湯気越しに定善の顔を見ていた。
二人が向かい合って座るテーブルの中央には白紙の原稿が置かれている。健斗はさりげなくそれを置きっ放しにしていただけなのだが、こうして二人でその真っ白な紙を見つめ合っていると、本当にそのただの変哲のない紙が白樺の用意した伝説の三十二ページ目のような威光を放つのだった。
「お断りなさるのならば、それはそれで構いません。印刷所に話せば、『ブルックリン・ブラザーズ』の最終回は三十一ページということにして製版して下さるでしょうし、三十一ページの遺作はめでたく雑誌に掲載されるでしょう。そして、この原稿を読んだ読者達は疑いなくこの作品が完結したものだという印象を抱きます。確信があります。白樺先生の残した三十一ページの作品は、非の打ち所のない最終回だと」
安堵しかけた健斗に「ですが」という鋭い一言が差し込まれた。
「この漫画が未完成だと知る人間が残ります。あなたのお姉様と、あなた、そして……私です」
威圧感のある言葉だった。定善はまるで健斗を圧倒しようとするかのように意見を連ねていく。
「私は少なくとも忘れないでしょう。国民的漫画家である白樺が最後に残した作品は、未完であったと。健斗さん、あなたはそれでよろしいですかな? 漫画の仕事に携わる者として、そして何より『ブルックリン・ブラザーズ』の愛読者として、それで後悔しませんかな?」
結局、定善は完成している分の原稿も受け取らずに帰っていった。コピーもとらず、ただ一度だけ原稿を読んで頷くと、健斗に全てを預けていったのである。
「恥ずかしながら、桃は好物ですので」と言って、阿久津からの差し入れである桃の缶詰を二十個ほど抱えて行った。
家を占領せんとばかりに増えていた缶詰は僅かながらでも減ったものの、代わりに健斗の心労は容赦なく増すばかりであった。
去り際に定善はこう言い残していった。
「覚悟が決まりましたら、ご連絡をお願い致します。『ブルックリン・ブラザーズ』の発売日、雑誌への掲載日はいつまでも伸ばせますが、限度もありますのでご注意を。健斗さんの気持ちが固まり次第、原稿作成の日程を決めさせていただきます。すなわち、締め切りの設定でございますね」
柔和な表情を終始崩さない定善に、健斗はつい上げ足を取るような質問を繰り出していた。
「締め切りの設定は必要なんですか?」
「ええ、『虎は追い立てられた時に猛虎となる』。飼われているような虎の生き方を見たいのではありませんので。私は、あくまでも猛虎の目を見たい。四苦八苦の中でも奮迅しようともがく、猛獣の姿を漫画家には期待しているのです。これはあなたにだけ求めていることではありませんよ。他の漫画家にももちろん要求します。無論、白樺先生にもです」
その言葉の中に健斗は定善があくまで僧侶ではなく、この漫画の世界で生き抜くプロであると認めるのだった。
だが、どうあれ健斗は困難との戦いを迫られるのであった。
三十二ページ目を描くか否か。
このまま三十二ページ目を白紙のままにして出しても、『ブルックリン・ブラザーズ』は完成を迎え、かねてより宣伝されていた白樺 春に原稿を託された男、山崎 健斗の名前は多大に評価されるだろう。
それのどこが悪いのだろうか。
そもそも健斗はそういう契約でもって、白樺と定善からこの原稿を引き受けたのではなかったか。
このままでも十分に健斗の名前は評価されるであろう。
それに『ブルックリン・ブラザーズ』も現状の三十一ページで綺麗に完結しているのだ。ファンも納得するに違いない。それは健斗自身もこの漫画のファンだったので分かる。
むしろ恐るべきは自分の手が加えられたことにより、名作に泥を塗るような結果となり、評価を下げてしまうのではということだった。
ここは動かないのが上策だ。
このまま三十二ページ目はなかったことにして、正真正銘、白樺 春の遺作としての『ブルックリン・ブラザーズ』を世に出そう。
健斗は自分に言い聞かせるように何度も頷いて、白紙の原稿を机から取り除くと、元通りに棚にしまいこむのだった。
そうと決まれば、白樺の原稿をさっさと定善に引き渡してしまおうと思った。健斗は仕事場に向かうと、引き出しにしまわれていた封筒を取り出して開封し枚数を確かめた。
確かに全て揃っている。『ブルックリン・ブラザーズ』の完全なる完結編である。健斗は改めて読み返してみても心から思うことが出来たのだった。これ以上、何を付け足せと言うのだろうか。
それにしてもこの『ブルックリン・ブラザーズ』は素晴らしい漫画だと健斗は改めて思う。余韻に浸っていると、つい最初から話を読んでみたくなり、仕事場の隣の部屋に足を運んだ。そこは本棚だけの部屋であり、姉弟はそこを「資料室」と呼んでいたのだが、資料となる背景写真集の他に漫画の類いも混ざっている。白樺 春の作品ももちろん揃っていた。
一巻を取るとそのまま床に座り込んで読みふけり始める。
その『ブルックリン・ブラザーズ』という作品は、少年誌「週刊シーポス」に十年前から連載されている。白樺 春のキャリアにおいてその後期を間違いなく代表するものだ。ジャンルは青春学園漫画。今時には珍しい、男同士の友情や異性との甘酸っぱい恋愛、そして喧嘩……学園生活をシリアスなタッチで硬派に描いている。コメディ要素の少なさからファンはコアな層に限られていたが、十年の時を経ることで、週間シーポスの様々な世代の男女の感性に浸透していき、不動の人気を獲得したのだ。
そして、何よりも舞台をニューヨーク州のブルックリンという街にしており、これまで学園漫画と言えば当たり前のように日本の学校が描かれていた訳だが、その点においても『ブルックリン・ブラザーズ』は評価されていた。ブルックリンという街を好きにさせるような仕掛けも満載だった。
ページをめくりながら健斗は過去の記憶をさらっていた。
アメリカの高校において存在するスクールカースト、それに立ち向かう主人公たちの闘争。ラフであって危うい雰囲気のする食生活。どれも健斗は憧れたし、一時は彼らのようにポロシャツの襟に丸い車輪のバッジを付けていた。
丸い車輪のバッジ。
それは作中で主人公達が「仲間の証」としてお互いに付け合う代表的なアイテムだった。
健斗は本から目を離すと、あのバッジはどこに行っただろうかと思い出していた。
そして、ふと気がつく。
どうして自分はそのバッジを持っているのだろうか。
いや、それはあくまでこの漫画のバッジに似たものを付けていただけだろう。どこかでそっくりの品物を見つけて購入したに違いない。
しかし、バッジをどこかの店で買ったという記憶が無い。おそらくあれは小学生の頃だったが、バッジの売っていそうな雑貨店に入った記憶も無いし、そんな店の存在も知らなかった。おもちゃ屋でグッズ商品としてそのバッジがあったのだろうか。それならば他の友人も持っているはずだが、思い返す限り、バッジをつけていて周りの人間にうらやましがられた記憶がある。と言うことは、自分だけが手にしていたようだった。
健斗は仕事場に戻って引き出しの中を探り始めた。
予備の画材が入った二つ目の引き出しは頻繁に使うが、それ以外のほとんど物置と化している三番目と四番目のエリアを探っていく。
すると、丸い車輪のバッジが見つかった。ピンの部分は錆びてしまっているが、表面は当時と何も変わらない輝きを放っていた。
バッジを持って資料室に戻ってバッジの出てくるシーンを読み返してみると、本の中に出ている品と自分の手にしているものがまるで同じものだと気づく。
この奇妙な偶然に、健斗は自分がこの漫画の中にいたような錯覚さえ感じるのだった。
完成原稿を前に仕事用の机に座って、バッジを眺めながら考えを巡らせる。
何故、こんなことが起こるのだろう。
自分と白樺との間に何かまだ知らない繋がりがあるというのだろうか。そこで彼は、自分が白樺の最後の作品を任された時に持った奇妙な感覚を思い出すのだった。
あの日、姉は白樺からのオファーを断って、アシスタントである弟を推薦した。もちろん断られるはずだったが、まるで白樺はそうなることが分かっていたかのように了承したのだった。
どうして白樺は自分のような実績も知名度も実力も無いアシスタントに最後の大仕事を任せたのだろうか。
健斗は腕組みをしながら考え込むが答えが出るはずもなく、コーヒーでも飲もうかと台所へ足を向けた時だった。スマホが新着メールの存在を知らせていた。どうせいつ登録したのかも忘れてしまったようなショッピングサイトからのプロモーションのメールだ。
それよりも気にとまったのは待ち受けになっている自分の写真だった。
別に好き好んで自分の顔を待ち受けにしている訳ではない。いたずらで姉が自分の寝顔を撮影し、それを勝手に設定したのだ。設定を解除しようとすると機嫌を損ねるし、さほどスマホに触るわけでもないので完全に今では自分の顔がそこにあることになじんでしまった。
自分の写真を見て閃いた。
リビングへと向かって、サイドボードの上に並んでいる写真のアルバムから一冊を取り出した。探すのは自分があのバッジをつけているものだ。
そうしてたどり着いたのは、小学生の時の遠足の写真だった。
浜辺の近くを走る電車を背景に、アップで撮影された幼い頃の健斗が映っている。何か遠くのものに意識を集中しているような顔をしていた。そして、その自分の服には……バッジが付いている。
そんな馬鹿なと思わず小さな独り言が漏れてしまった。
これは小学生の時の遠足の写真だ。それも低学年のものである。『ブルックリン・ブラザーズ』が連載を始めた頃のものではないだろうか。
その時、あの漫画にはこのバッジは出てこない。
つまり、健斗は『ブルックリン・ブラザーズ』で車輪のバッジが出てくるより前に、この手の中のバッジを持っていたのだ。
すっかり混乱してしまった健斗はリビングの椅子に座って腕組みをして、一旦落ち着こうと試みる。
目の前にあるのは、写真のアルバム、そして『ブルックリン・ブラザーズ』のコミックス、いつも服に付けていたバッジだった。いくつもの謎のかけらが健斗に何か途方もなく巨大な事実を隠しているような気がしてならない。
しかし、これ以上は考えていても埒があかない。
迷った末に健斗は定善に電話をすることにするのだった。
「おや、覚悟が固まりましたかな。猛虎になる準備も出来ておりますか?」
「……奇妙な話をしても良いか」
喉の奥から声をひねり出すようにして言った。それによって電話口の向こうの定善もこれは原稿の話ではないと察したようだった。しばらくの間があってから「構いませんよ」と返答があった。
「ひょっとしてなんだが、白樺先生と俺は過去にどこかで会っていたりするのか?」
「何故?」
そう尋ねられて健斗は『ブルックリン・ブラザーズ』に登場するバッジと自分の幼い頃の写真、そして作中でバッジが出る前に自分がそのバッジを持っていて身につけていたことを話した。
すると、定善は満足そうにため息を吐いてから、「今からそちらに向かう」と口早に言って電話を切るのだった。
定善は袈裟姿ではなく「坊主」と描かれた真っ赤なTシャツにチノパンを履いてきていた。何か一言、コメントを入れた方が良いかとも思ったが、健斗はそのまま彼を迎え入れる。原稿についてのやり取りをした時と同じように、リビングで向かい合うのだった。
「あなたが疑いを持った時には遠慮無く話して欲しいということでしたので、私はこれから白樺先生の遺言に従いましょう」
「遺言? 先生は、遺言を残さなかったのでは?」
「漫画に関しては、です。これから話すことは漫画については一切関係の無い、先生の個人的な問題についてのことです」
「電話口じゃ駄目で、しかも……そんな格好で人前に出なければ話せないこと、か」
「袈裟姿は私にとってはスーツ姿に近いですからね。これはあくまでもプライベートの証なのですよ」
健斗は彼があくまでも真面目にこんな服装をしているのに驚いていた。
「あなたがバッジをしていること。そして、『ブルックリン・ブラザーズ』にそれが登場すること。少しのこじつけで真実は見えてきますよ」
「こじつけ?」
「そうです。山崎健斗さん、あなたはこの『ブルックリン・ブラザーズ』の主人公なのです」
時が止まったかと思った。
相手の言葉を受け入れるかどうかという問題よりも、頭が一瞬真っ白になってしまって、何一つ情報が残らない状況が生まれてしまった。それによって思考がぴたりと停止してしまった。
「お、俺は……この漫画の中の登場人物なのか?」
「混乱されているようですな。正確には、あなたはモデルです。先生はあなたをモデルにしてこの漫画を描いたのです。あなたが辿るであろう人生を想像しながら、その姿を漫画の形で予言したのです。もしくは願望したのです」
「どうして白樺先生はそんな……そんなことをしたんだ。どんな理由があって、そんな、人の運命を、俺の人生に思いを巡らせるようなことを」
「それは白樺 春先生は、あなたの本当のおじいさまだからですよ」
「お、おじいさま? 祖父ってことか?」
健斗の言葉の後でゆっくりと定善は頷いた。
白樺は健斗の血縁上の祖父であった。
健斗は自分の両親から祖父母の話を一切聞いたことがなかった。物心ついた時から会ったことはなかったし、両親も口には出さなかったので、きっと自分が生まれる前に亡くなってしまったのだろうと勝手に思い込んでいたのだ。だが、事実はそうではなかった。
一ヶ月と少しの間だが、一緒に漫画を作っていたその時。
それこそが健斗の中で祖父の存在を最も近くに感じていた瞬間だったのだ。
「信じられないのはごもっともです。ご本人も、写真でしか健斗さんの姿は見たことがないと仰ってましたし、自分に孫がいるのも信じられないと亡くなる直前に話していました。ですが、証拠はございます。もしも、健斗さんが望むのならば、あなたのお父様と白樺先生の関係についての法的な証明書を取り寄せられますが」
「いや、いらない。それは後でもいい」
健斗は机の上で組んだ自分の手に視線を落としていた。胸の中身がどこかに吸い込まれようとしているかのように強く引っ張られるのを感じていた。暴れようとする感情が落ち着くところを探してうろついている。
白樺が自分の祖父。そして、『ブルックリン・ブラザーズ』の主人公のモデルが自分。
とっちらかった思考の中で、すきま風のように声が聞こえてきた。
自分の描いてきた原稿を見て感想を述べる白樺の、一つ一つの言葉。
何もアドバイスはしてこなかったけれど、決して彼は無口だったわけじゃない。健斗は彼から受け取っていた多くの言葉を思い返して拾い集めていた。どれ一つも忘却したくない。一度捨ててしまった貝殻が、海辺で最も価値のあるものだと知らされた時、きっと人は砂浜をもがくように自分の捨てたものを探るだろう。
健斗は同じように記憶を拾って拾って……大事に胸にしまっていく。
どうして自分が『ブルックリン・ブラザーズ』を好きになったのか。
当たり前だ。
その話は、誰かに願われた自分の幸せの物語だからだ。
それが好きにならないわけはない。好きになれないはずはない。
――漫画を描いている時が一番病気を忘れるよ。朝食はバナナだけでいい。面白い話はすぐにメモしとこうと思うんだが、メモの無いところで話は生まれるから困る。海に行ったことはあるかな? アメリカに行きたいと思う? フットボールは好きかな。贔屓はどの力士だ? 今日は呼吸が苦しいけれど、一番頭がすっきりしている。君の描く漫画は線が好きだ。正直だ。
そうだ、祖父は自分の絵を好きだと言ってくれた。
健斗は自分に向けられた最期の言葉を思い出す。それは原稿の完成間近、打ち合わせの途中で昼寝を始めてしまった白樺を見て、迷った末にこっそりと病室を出ようとした時だった。
去っていく健斗の背中に言葉がかけられた。
「漫画が好きで良かったな。お互い」
自分は何と返事をしたのか、健斗はどうしても思い出せない。
漫画が好きで良かった。
漫画を描いていて良かった。
その通りだ。
そのお陰で自分は祖父に出会えたのだから。
健斗は知らぬ間に自分の手に涙が落ちていくのを感じていた。しかし、それを隠すことはしない。涙を拭う代わりにこう切り出した。
「『ブルックリン・ブラザーズ』の三十二ページ目を俺に下さい。今からでも描きます。この場で描いてみせます」
掲載された『ブルックリン・ブラザーズ』の最終回を読み終えて、姉の十音はしばらく何かを考えていたようだったが、目の前で健斗が張り詰めた表情をしているのに気がついたらしく、薄らと笑ってみせた。
「そうなのね……このお話、こういうことになるのね……」
十音はイタリア旅行から先日帰国し、早速健斗の描き上げた『ブルックリン・ブラザーズ』の最終回を読んでいた。雑誌の発売に合わせるかのように彼女は帰宅していた。
「……姉さんは知っていたんだろう。白樺先生が俺たちの祖父だってことをさ」
「さて、どうかしらね」
彼女は遠くを見つめるように視線を逸らした。これは間違いなく事前に知っていたなと健斗は感じるのだった。
「でもね、きっと健斗にとっては良いきっかけになると思ったわ。白樺先生側から申し出があった時、直感したのよ。そして、それは間違いではなかった」
健斗は姉から真っ直ぐに自分の瞳を見つめられた。
今、まさに彼が腹の底に抱えている思いを把握していると言いたげだった。加えてその言葉を誘い出そうとしているように、優しい間がこの空間には置かれている。
一度咳払いをして、健斗は切り出した。まるで姉の好意に甘える形で。
「俺、ここを出て、アシスタントを辞めたいと思うんだ」
「漫画はもう描かないのかしら」
「逆だよ。漫画を描くんだ。俺は、俺で漫画を描いていきたい。名前も変えてさ、新しくこの道を歩いていきたいんだ」
そう打ち明けた健斗を十音は『ブルックリン・ブラザーズ』を読み終えた時から全く変わらない表情で見つめ続けていた。
「困るわね。これから食事はレトルトばかりになってしまうわ。缶詰の処理も、どうしたら良いのかしら」
十音のそんなとぼけた返答に健斗はリビングを見回して答えた。
「姉さんも料理を覚えなよ。それにたまには帰ってくるし、缶詰は……うん、何とかする。具体的には阿久津さんを何とかするよ」
そう言って、二人は笑い合うのだった。
こうして漫画家、山崎十音のアシスタントであった山崎健斗は独立した。
数年後、彼は祖父のペンネームであった白樺の名を借りる形で、「白樺健斗」として漫画家デビューを果たす。
彼の最初の作品は凡庸な西部劇で人気が思ったより上がらず、すぐに連載が打ち切りになってしまった。次にミステリーものを描いたのだが、それも読者に受け入れられず、ホラーやラブコメにも挑戦するがどれも鳴かず飛ばずに終わる。
それでも白樺健斗は諦めることがなかった。
現在は冒険海洋ものを企画し、これが上手くいくかどうかは本人にも誰にも分からない。
不安になる時も絶望する時もあるが、彼には『ブルックリン・ブラザーズ』で自らが描いた三十二ページ目に常に励まされてきた。
祖父の紡いだその物語の終わりは、美しい一枚絵で幕を閉じた。
丸々一ページを使った、セリフも何もない巨大な絵。
それは二人の白樺という漫画家が共に見た、ブルックリンの美しい朝焼けの風景だ。
朝日の当たる部分と当たらない部分の波はトーンのグラデーションで丁寧に仕上げられており、船着き場の倉庫は一つ一つが精密画のように表現されている。対照的に空は大胆な筆使いで描かれていた。Gペン、ミリペン、そして筆ペンまでを動員してありとあらゆる線で描かれた風の流れ。
その渾身の一枚はファンの間で「白樺 春」が最期に読者への礼として手向けたメッセージであり、これからも自分の作品を愛して欲しいという遺言なのだとされていた。
しかし、それは間違いだ。
このページを描いたのは白樺健斗で、絵に込められたのはもっと別の想いだ。
物語はまだまだ続く。こうして自分が最期のページを用意したことで、『ブルックリン・ブラザーズ』は終わらない。懸命に彼が筆を動かしながら考えていたのは、そんなことであった。
そして、今もまだ物語は動き出そうとしている。
おわり