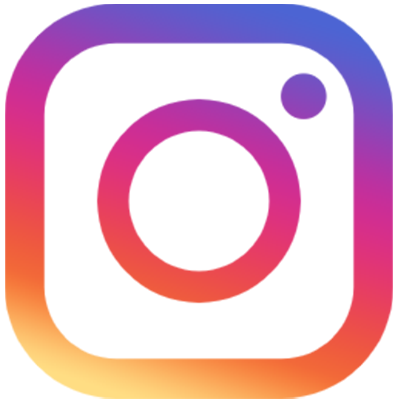毎月23日は小説の日!【託されたラストページ(前編)】
漫画家の白樺 春が亡くなった。
彼の死はすぐさまテレビでもネットでもラジオでも速報で伝えられた。
どのメディアも惜しみつつ彼の偉大な功績を称え、茶目っ気たっぷりのコメントを送っている。
「先生は今頃、同じ漫画家の赤田さんや照川さんと一緒に、お酒を飲みながら談笑されているでしょうね」
そんなラジオのコメンテーターの話を耳にして青年が顔を上げた。彼は机に向かって何かを懸命に描いていたが、悪霊に憑かれているかのような足取りで立ち上がって、ラジオの前に立つ。
繰り返されるニュース。
漫画家、白樺 春の逝去。
青年は改めてそれを耳にすると呟く。
「亡くなられた。先生が……亡くなられた?」
それっきり言葉を失ってしまう。ラジオはそんな青年に無慈悲にも言葉のシャワーを浴びせ続けていた。白樺の功績や死因、そして過去の名言やワイドショーを賑わせた女性関係のスキャンダル。
そして、話題は青年の心臓を強く鷲づかみするようなものへと変わっていく。
「ところで、白樺先生は人気シリーズ『ブルックリン ブラザーズ』の完結編を執筆されていたそうですが、それはどうなるんでしょうねえ。私、『ブラブラ』は学生時代からのファンなんですよ」
まだ若いが青年よりは年上であろうパーソナリティは無邪気に語っていた。
「どうなるんだよ、これ……。最後までふざけるなよ、あのじいさん……」
青年はラジオから振り返って、先ほどまで描いていた紙を見る。それは紛れもなく本物の「ブルックリン ブラザーズ」の原稿だった。
ラジオのパーソナリティが楽しみにしている漫画の続きは、この青年が今しがた仕上げているものなのである。
青年の名前は山崎健斗。
人気推理コミックス「イービル・エージェント」の作者を実の姉に持つ、漫画家の卵であった。
「そう……。白樺先生は亡くなられたのね。大学書房の足塚漫画賞の授賞式でお会いしたこと、昨日のように思い出すわ。……お前みたいな勢いだけの漫画家は半年で消えると激励されたこと、今でも夢に見るもの」
パソコンのビデオチャットを通してそう話しかけてくる女性は、どこか含み笑いでもしているかのように表情が明るい。話しぶりからはあまり仲が良くなかったようだ。
「姉さん、頼むからマスコミの前じゃそんな明るい顔を見せないでくれよ。訃報のニュースで流れるんだぞ。たちまち炎上沙汰だぞ」
健斗は苦言を呈しながらパソコンの脇に付いたマイクに話しかけていた。
今、彼の目の前の画面にいる人物こそが、姉の山崎十音である。十代にして週刊誌への連載を開始し、幾度となく物語を完結させては、また次の作品へと取りかかっていく。その無尽蔵のアイデアと生産力から、業界内では「コミックタイフーン」と呼ばれていた。
健斗はさすがに姉を自然災害呼ばわりするのはどうなのかと思っていたが、当人は自分が何と呼ばれるかなどまるで興味がないようだった。
十音にとっては漫画以外の全ては「背景」に過ぎないのだ。人生を引き立てはするが、決して自分の前には来ない。
そんな心理の持ち主だからこそだろう。今、十音は次の漫画の取材のためにヨーロッパを歴訪している。編集者たちは十音の旅立ちを止めて、一刻も早く次の漫画を描かせたかった。当然だ。出せば売れる作家をわざわざ温存したくない。
しかし、言い出したら聞かないのも十音である。
「少し、世界を見てみたくなりました」
その言葉の次の日には十音はイタリア行きの飛行機に乗り込み、誰の手も届かないところに旅立ってしまっていた。
「それで、姉さんはどこにいるんだ。『イービル・エージェント』が終わってからファンレターも倍増してて、いい加減、置き場に困っているんだが」
「勝手に捨てては駄目よ。しっかり読んで心の中でお返事を書いてあげて、相手の心に送ってあげてるんだから。阿久津さんの持ってくる乾パンと桃の缶詰なら捨ててもいいわ」
「それこそ捨てちゃ駄目だよ。食べ物は大事にしないと。それに、返信も心なんかじゃなくて、直接書いてあげたら喜ぶんじゃないかな」
「阿久津さんに悟られないよう工作してくれるのかしら。見つかったら結構本気で怒られるのよ。『ファンへの返事は大切ですが、それよりうちの原稿をお願いします! あと、カニの缶詰どうぞ!』ってこの前『ぱわはら』を受けたわ」
「缶詰を押し付けるのもパワハラ認定される時代だね……。とにかく缶詰は最近俺が食べてるんだ。捨てたりしないよ、無駄にはしない。ファンレターと缶詰で部屋が占領される前に何とかしてくれよ」
阿久津というのは、二人の担当編集者である。月刊モーニングスターで連載していた『イービル・エージェント』が始まった頃からの付き合いであり、歳は十音よりも一つか二つ上の二十代後半。作品への口出しはほとんどしないが、差し入れは毎回する担当編集者だった。連載が終わった今も、次の連載を早くしてくれと家に押しかけてくることが多い。
もっとも今は十音が旅行中なので、家を訪れる回数は減った。
「それで、何かしら。その気難しい感じだと、私に話したいのは白樺先生が亡くなったことだけではなさそうね。もしかして、頼んでおいた『月の満ち欠け記録』を忘れたとか、そんな悲しいことを伝えるわけではないわよね。帰ったら日本の月の運行と、イタリアの月の運行とを見比べるのが楽しみなのだから。怠っていたらお土産は抜きよ」
「それはちゃんとやってるよ。白樺先生から頼まれている『仕事』について困っている、というか、弱っているというか」
先日亡くなった白樺 春から、健斗は重大な仕事を請け負っていた。
それはまだ白樺が病床の中でも起き上がって漫画が描ける状態だった時のことだ。
彼らの家を定善という名の漫画編集が訪ねてきた。袈裟姿で坊主頭だったので彼をお坊さんだと勘違いしてしまった。
モーニングスターとは別の出版社で編集者をしている定善は、健斗と十音にこう切り出したのだった。
「現在、白樺 春が取りかかっている『ブルックリン ブラザーズ』の完結編。その完成にお力添えをお願いたい」
健斗は坊主に頭を下げられるのは初めての経験であったが、彼は本職の坊主ではないのだと認識を正すと、相手の要望について検討を始めた。
確かに今、姉の十音は「イービル・エージェント」の連載を終えた。これからいくらでも手は空くだろう。
それに白樺 春と言えば、何度もテレビで密着取材を受けたりバラエティにも出たりしている国民的な漫画家だ。作品は英訳されて海外にもファンがいる。
そんな著名な漫画家の作品を手伝えるのならば、これほど名誉なことはないだろう。
是非引き受けるべきだと健斗は姉に助言しようとした。
だが、その前に姉の十音は首を振って「私はこれから世界を見にいくのでお断りします」と即断に近い断り方をしてしまった。
突っぱねるような姉の言い方に健斗はぎょっとしていたが、そのすぐ後で、さらに耳を疑ってしまうような言葉が発せられるのであった。
「是非、私の弟の健斗をお使いください。腕は確かですよ。それに、私が旅に出ている間、彼がやることは部屋に転がった缶詰を食べていくことだけですから」
気まぐれとも言える言葉で推挙されてしまった健斗だったが、自分が断るまでもなく相手の方から話を破談にしてくれると思っていた。なので、「そちらさえ良ければ微力を尽くされていただきます」と返答してしまった。
それが間違いだったのかどうか今でも彼は自問をするのだが、とにもかくにも先方からの返事は「是非ともお願いしたい」とのことであった。
まさか万年アシスタントとして漫画に携わってきただけで、独立した自分の作品など書いたことなどない自分に仕事を任せるとは夢にも思わなかった。
しかも、相手は国民的な漫画家の白樺 春だ。
話が決まってから、これは何かのいたずらかドッキリではないかと健斗は疑った。
その疑念を綺麗に晴らしたのは、病床にて机にかじりつくように鉛筆を動かす老人を紹介されたことだった。
命を振り絞るようにしてケント紙に鉛筆を擦り付けるその男こそ、漫画家の白樺 春。出会った瞬間に健斗は圧倒された。
彼こそが漫画の神様だ。
もしくは世の中に素晴らしい漫画をもたらすために神がこの男を生み出したのだ。
大げさにもそう思えるほど、健斗は白樺を尊敬するようになったのだった。
健斗は再び姉に状況を説明し始める。
「亡くなる直前まで先生は原稿を描いてて、下書き自体は全て終わってるんだ。手元には今、『ブルックリンブラザーズ』の最終話の原稿が全て揃ってる。後は俺がペン入れをして仕上げてしまうだけなんだけど」
「順調で何よりね」
「原稿が一ページ足りないんだ」
健斗は画面の中の姉の目から視線を逸らさずに訴えた。本気で困っていると訴えるためだ。
「足りないというのは、完成していないということかしら」
「いや、話自体はきちんとまとまってる。でもさ、確かに何度も繰り返し、先生は俺との打ち合わせで『最終話は三十二ページだ』って繰り返してたんだぜ。なのに、俺のところにあるのは三十一ページ。病院の人もご家族も病室をくまなく探したらしいけどさ、見つからないんだ。三十二ページ目が」
早口で伝えると、十音は遠い目をして何かを考えている風であり、それから話を切り出した。
「あなたはどう思うのかしら。三十二ページなくても完成しているなら、編集のお坊さんに話をすれば解決するわ。でも、あなたはそうしなかった。そうしないで、私の前で弱っている。ねえ、漫画は完成したの?」
「違うよ、姉さん。話はまとまっているだけだ。三十一ページで最終話が出来た。でも、その最後のあるべき一ページがないと、漫画は完成とは言えない。だって、あれだけ繰り返し繰り返し、三十二ページだ、三十二ページだって話してたんだぜ。『これが人生最後の三十二ページだと考えると、儚いようで充実しているようでもある』って。うっかりしていたなんて考えられない」
健斗は強い口調で言うと、十音は嬉しそうに表情を緩めて言葉を返す。
「それでこそ、あなたを白樺先生に紹介した甲斐があったわ。実を言うと私はその三十二ページ目の在り処が分かる気がするの」
「分かる? まさか先生と何か話をしてたのか?」
「するわけないじゃない。不本意極まりないけど、先生の心が少しだけ理解できるの。三つだけ質問に答えてもらえるかしら。それがあなたにとってもヒントになるわ」
十音は思わせぶりな口調で述べると、人差し指を立てた。
「先生の原稿を仕上げている中で、何か注意されたかしら? 例えば、自分の絵が出すぎている……とか、こんなのは自分の絵じゃないとか」
「なかったな。そりゃ俺だって努力したから。先生の作品を見て、何度も模写して絵柄を近づけたんだ。仕事は完璧だったぜ。先生はどれも黙って採用してくれてた」
「二つ目。今ある最後のページ……つまり三十一ページは先生から直接もらったのかしら」
「いや。亡くなってからご家族が渡してくれた」
「最後よ。白樺先生の、あなた宛への遺言みたいなのはなかったかしら?」
ここまであらゆる質問には即答できていたのだが、ここに来て健斗は答えに詰まった。
白樺と過ごしたのは一ヶ月あまりになり、そのうち顔を合わせたのは七日ほど。
会ったとしても世間話などせずにすぐに漫画の話を始めていた。
健斗も健斗で自分に託された仕事の大きさに潰されないようにするのが精一杯だった。必死に失敗をしないようもがく中で、自分が何を掴んでここまでやって来たのか、ようやく今になって考えるのだった。
自分に何度も投げかけられた言葉。
深く息を吸って目を閉じてみた。耳の奥から声の記憶を取り出す感覚、そのイメージに意識を集中させていく。
穏やかだけれども、うねる様に厳しさのある言葉。
分かりやすいけれど、いきなり難解になる問いかけの数々。
先生の言葉はいつも二面的だった。
その中で健斗は最も頭を悩ませた、先生の最期の言葉を思い出した。
話の終盤。主役級のキャラが三名で会話するシーンを描いている時だ。新たな旅立ちを示唆するセリフと共に、その言葉を発したキャラの表情について先生はこう告げたのだ。
「主人公のこの決意しきっていない顔はいい。絶対に後戻りできない状況で、この中途半端な顔。でもな、次に描く時はもっと強い意志を込めるんだよ」
その時は素直に受け止めた健斗だったが、先生から離れて一人で原稿を仕上げながら首をかしげるようになっていく。
何故なら、先生が言う様な次に描く時……つまり、続くページにてキャラが決意を表明する場面など出てこないからだ。
その「次に描く時」という白樺の言葉が強く残っていたので、健斗はこれが自分に残された言葉なのだと判断する。そして、十音にそれを告げた。
すると、十音は満足気に頷いて告げる。
「全部分かったわ。あなたの望む、三十二ページ目の場所。あなたには分かるはずよ。分かるかしら?」
得意気に十音は告げてくるが、健斗にはまだ分からない。
正解を掴んでいるという予感はあるが、確かな自信だけがなかったのである。
果たして白樺 春の漫画『ブルックリンブラザーズ』最終話の最終ページ、三十二ページ目の原稿用紙はどこにあるというのだろうか?
続く