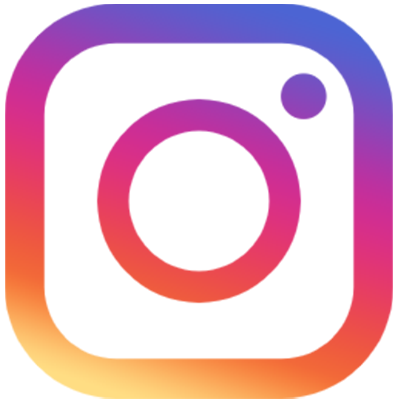毎月23日は小説の日!【ブルックリンブラザーズ(後編)】
まもなく時計の針が頂点に達しようかという夜半頃、高校の校舎前でニッキーは場の空気を伺っていた。
一ヶ月前に起きた、エリスという生徒の死亡事故。原因は図書室の本棚が倒れ、その下敷きになったことだ。死亡「事故」とはなっているが、それは暫定であり、事故かはたまた事件かの見解も警察から出されてはいない。そんな状況にあって、ニッキーとその弟のラルフ、そして友人のゴルゴはある人物を「犯人」として疑っていた。
その男の名はギルバード。
エリスが亡くなったことでギルバードは「州立大学の給費学生」に繰り上げ合格していた。給費学生というのは高校から大学に推薦される生徒のことで、選ばれれば学費を免除されて州立大学に通うことができる。ギルバードはこの高校からの推薦に惜しくも漏れていた。今回のエリスの死亡によって席が一つ空いたことにより、彼はその椅子に座ることができたのである。
その点を「疑わしい」と感じたニッキーの弟とその友人は、独自に聞き込みを開始したらしい。それによって今夜、ギルバードを図書室へと呼び、彼の殺害のトリックを暴いた。
……はずだった。
ニッキーの弟、ラルフ。そして、二人の共通の友人であるゴルゴ。
彼らが持ち出した様々な人の証言は、確かに犯人をギルバードだと示している。
だが、いわゆる物的な証拠というものは一つも見つかっていないのだった。
ニッキーはその点がもしかしたら、ギルバードの今の態度に繋がっているのではないかと思っていた。
犯行を推理によって指摘されても、毅然とした態度でギルバードは立っている。「通報したいならしろ」とも言っていたはずだ。
はったりなのか、苦し紛れの強がりなのか。どちらにしてもニッキーはそんな態度をとる彼を安易に犯人だとは考えられなかった。
「兄貴、悪いな。母さんには少し遅くなると伝えてくれよ。こいつに付き合うぜ」
闇の中で弟のラルフがスマホを出した。
この場で通報するつもりであろう。向こう見ずな行動を取りやすいラルフなら、十分にあり得る。
ギルバードはそれでも「やれるならやってみろ」という顔を崩さない。
一旦歯を食いしばり、ニッキーは二人の間の緊張しきった空気の中に飛び込んだ。
「待ってくれ、まだ聞きたいことが残ってる」
一堂の視線がニッキーに集まった。
誰もが圧をかけるように彼を見つめる中、思い出すのは映画の一シーンだ。これまでの流れを変える時の、主人公の勇気に満ちた言葉、そして態度。
ニッキーが真似しようとしたのはそれだった。
「ギルバード、お前はどうして給費学生になりたかった? エリスを殺してでも大学に行きたい理由はあるのか」
改めてニッキーが尋ねたのは「動機」だった。何を今更という顔をゴルゴはしていたが、ラルフの方はそうではなかった。真剣な顔で彼の回答を待っているようだった。
「お前が給費学生に手を上げてるってことは、何かしら理由があるんだろ。それは誰かを傷つけてまで叶えたい望みだったのか」
給費学生に繰り上がりで合格した。
ギルバードのそんな状況を聞けば、反射的に彼がエリスを排除したのではないかという予想が浮かぶ。
だが、問題はギルバードの本当の動機だった。給費学生にならなくてはいけない。人を殺しても選ばれなくてはいけない。そこまで彼を追い詰めたものは何なのか。それが明らかになるまで、ニッキーはギルバードを犯人とは決めてかかれなかった。
「別に給費学生で選ばれなければ、どこかの大学にローンで入るだけだ。家からの援助は最小限にしたいんだよ」
すんなりとギルバードは答えた。
「信じると思うか? ああ、おおよそ進学を反対でもされて、最後の望みの綱として給費学生に申し込んだんだろう?」
「違うな。家族はむしろ俺の大学進学に賛成だ。帰りに会って話してみるか? それに、別の大学のローンについて放課後、パソコン室で調べてた。履歴は残ってると思うし、担任の教師にも話はしてあるぞ。明日にでも確かめてみるといい」
彼の言うように、初めて会った時もパソコン室で何か調べ物をしていたし、ラルフやゴルゴが集めてきた情報でもここ最近はパソコン室に出入りしていたとある。
「なあ、兄貴。証言や状況証拠は十分なんだ。あとは警察に任せようぜ。調べてもらえばきっとゴルゴの言うように、本棚を倒したロープだって出てくるぜ」
本棚を倒したロープ……。
それについてもニッキーは思うところがあった。
先ほどのゴルゴの推理によれば、被害者が下敷きになった本棚は図書室の「外」から引かれた一本のロープによって引き倒されたことになっていた。
ゴルゴの言うように、それならば色々なことに辻褄が合う。
クラスメートの誰もが本棚が倒れた原因を話せないのも、そしてエリスだけをうまく狙って本棚と本棚の間に誘導して倒れさせたのも。誰にも見られそうにない場所からロープを引けば、全て解決だ。
だが、ロープを所有することだけがその推理において「犯人」を決定する要素だろうか。
何か引っかかりを感じて考え込んでいると、ゴルゴがからかうように笑いながら口を挟んできた。
「おいおい、ニッキー。どうしたってんだよ。なあ、こいつに何か恩でもあるのか? ははは。まあな、確かにこの場で通報ってのは少し急ぎすぎかもなあ。それなら明日でも良いんだぜ。こっちにはまだまだこいつが犯人かもしれないって情報があるんだからよ。今日のところは家に帰ってよ、そうだ、バスケの試合でもネットニュースでチェックしてよ」
それでは駄目だとニッキーは考える。
明日に全てを持ち越すということが、ニッキーとゴルゴにはできるかもしれない。
しかし、弟はどうだろうか。
ラルフはほぼ彼の中で犯人だと確定しているギルバードを、一晩自由にすることを良しとするだろうか。
今この瞬間にも警察への番号をダイヤルしようとしているラルフを、そのまま家に帰したらどうなる。
確実にラルフはギルバードを通報してしまうだろう。
ここで容易に弟を帰してはならない。少なくとも何か「ギルバードが犯人ではない」という疑いのようなものでも植え付けなくてはいけない。
弟に無実かもしれない人間を突き出させる。そんなことになって欲しくなかった。
何か言いたげにこちらを見つめてくるラルフに対して、早急に何か言葉をかけてやらなくてはならない。しかし、とっかかりが掴めない。彼の目は訴える。何も言うことが無いんなら、通報させてくれよ、止めないでくれよ。不満と焦りのないまぜになったような表情がニッキーの全身にのしかかってくる。
こういう時、自分の敬愛する映画の中のスターなら、一体どんな、どのような言葉でもって状況を切り抜けるだろうか。
「一つだけ、思うことがあるんだ」
自然に口をついて出たのは、そんな一言だった。
導かれるようにして語句は並んでいく。
「どうしてギルバードを犯人だと考えるようになったのか。そして、そんな考えを俺が何となく受け入れられない理由が……どこかにあるんだ」
ニッキーはここ数日で起きた出来事を振り返り、ギルバードについて考え続けた日々を反省して、ようやく自分のするべきことに気がついた。
これまで、目の前で繰り広げられるドラマを、まるで映画を観るかのように傍観しているだけだった。
ここからは違う。
自分の胸に手を当てて、いくつも刺さっていた「違和感」という名前の棘を引き抜く
そんな使命感に目覚めた時、ある錯覚に陥る。
自分の視界の上と下に黒々とした帯が出現した。まるでそれは映画のスクリーンだった。
「最初に……ああ、そうだな、ギルバードがエリスを知ったという件だ。ゴルゴがあの男、名前は……ゲイリーだったな、ゲイリーからギルバードのことを聞いた動画があったよな。あれを見た時から少し気になっていたんだ」
ゲイリーとはゴルゴの知り合いであり、彼をインタビューした動画がニッキーたちには見せられていた。その内容は、「ギルバードがエリスの給費学生内定を祝うパーティに出ていた」と述べるものであった。
このゲイリーのビデオの存在と、さらにエリスのパーティ会場で撮られた写真に写っていたギルバードの姿。
これによって「ギルバードはエリスが給費学生に選ばれた」ということを知ったのだそうだ。
その二つの証拠にニッキーは疑問を抱いていた。
「もう一度、見せてくれよ。最初に見た時から気になってたことがあるんだ」
ニッキーがそう迫ると、ゴルゴは神妙な顔つきでスマホを渡して動画を再生するように言う。何度か観るうちにやがて違和感の正体が明らかになり始めた。
最初にこの映像を見せられた時、そしてギルバードに証拠を示すように言われてもう一度見せられた時。この二回の機会で、状況は異なっていたのである。
「音だ」
ゲイリーがにこやかに語り続ける映像を見続ける中で、気づいたことを反射的に口にしてしまっていた。
「音がどうかしたのかよ、兄貴。音量上げてくれ」
「なあ、最初にこの動画を見た時、俺たちは音を聞かされた。けどよ、ギルバードにこの動画を突きつけた時……音は出てなかっただろ?」
記憶を再生しながら言う。
そう。
ギルバードはパソコン室にいたので、その場で動画の音声を出すのは迷惑になると考えたのだろうか、ゴルゴは「音をオフにして」動画を見せたはずだった。
「そこに違和感があったんだ。ちょっと聞いてみてくれ」
改めてギルバードに動画を「音声込みで」観せると、すぐに感じたであろうことを伝えてきた。
「これは……ゲイリーの声ではないな。もっとしゃがれた、特徴的な声だったはずだ」
「分かったぜ。これは、映像と音声が合ってないんだ。本当にうまくしゃべっている瞬間に別の音声をかぶせてるけど、これは別人の吹き替えだ」
ニッキーは頻繁に英語以外の言語で作られた映画を観ていた。元の言語のニュアンスを知りたいという意図から、字幕にて鑑賞することが多いのだが、時折吹き替えの役者に気になった人がいると、英語の吹き替え版を選ぶこともあった。その回数も頻度も高かったので、ゲイリーの映像に別人の音声がかぶせられているのに気づくのは難しいことではなかった。
ニッキーの指摘に対してゴルゴは両手を広げて訴える。
「そいつあ心外だぜ。なあ、この動画はよ、俺がインタビューして撮影したもんなんだぜ。お前らだって確認したろ? ゲイリーのところに行って、インタビューの話をしただろ。それに、音声をいじるなんて魔法みたいなこと、できやしねえよ」
同情を誘うようなゴルゴの笑顔に、ニッキーはつい態度を軟化させてしまいそうになったが、それでもまだ告げなくてはならないことがある。
「エリスについて話してるにしては、その動画、ゲイリーの表情が明るすぎないか」
ぽつりと述べたニッキーの言葉に、皆の視線は動画へと集まっていく。画面の中のゲイリーは身振り手振りを付け加えながら意気揚々と話しているように見える。
これが、亡くなった生徒に対するインタビューだろうか?
「俺たちがゲイリーの所に行った時……確かにインタビューについての話はしていた。けれどな、ゴルゴ。お前はそれが『何のインタビューか』はゲイリーに言ってなかったな。しかも、音声まで消していた。それは、要するに……この動画を偽造した……からじゃねえのか」
自らの言葉によって、自らの抱いていた靄のかかった気持ちが晴れていく。
ゴルゴが手にしている動画は今や怪しげな存在になっていた。
そして、彼はその先を告げたくはなかった。導かれる答えが自分にとっても、そして弟のラルフにとっても辛いものになると分かっていたからだ。
「おいおいおい、やめてくれよ。ゲイリーはちょっと空気読めないやつでよ。見方によっては少し不自然だけど、それでも動画の中にはしょんぼりしてるところだって何箇所か……」
そう弁明をし始めるゴルゴだったが、場の空気の変化に彼も気がついてふてくされたような顔になっていった。
それでもニッキーはその先を告げなくてはならない。
弟の無茶を止めるための、とどめとなる一言をこの場に放つ必要があるのだ。
「これでゴルゴの証拠の怪しさは分かったろ。ギルバードの不審さと、ゴルゴの不審さ。これで事件はまだ結論が出なくなったな」
ニッキーはそれだけ言って、自分の推理を辞めにしたかった。これ以上、この件について考えたくはなかった。さしあたっての目的は達成されたのだ。これでラルフも警察への通報は思い留まるだろう。
その先は何も望んでいなかった。
しかし、思惑通りにはいかない。
「その先も教えてもらいたいものだな。まだあるだろう。色々とおかしな点が見つかったはずだ」
場に新たな言葉を加えたのはギルバードだった。
「お友達の口から言い出せないのなら、俺から告げるまでだ。ゴルゴ、そしてラルフ。お前らの行動や言葉には看過しがたい嘘が混じっている。その点について話そうじゃないか」
これまでのギルバードとは様子が違っていた。表情を見ると、常に歪んでいた眉間のあたりは更に険しく深みを増し、これまで周囲を観察するばかりだった眼光は確かな獲物を見つけたように厳しく二人の人物へと向けられていた。
厳かな動きで彼は右腕のストップウォッチを起動させると、早速言葉を紡ぎ出した。
「初めに俺に話しかけて来た時から、怪しいとは感じていたんだ。給費学生のリストを見せられたが、あれはどこで手に入れたものなんだ? ……教師にしか閲覧できないものなんじゃないか?」
ギルバードが述べたのをきっかけにニッキーは記憶を辿る。
ゴルゴとラルフがパソコン室にいる彼に話をしようと持ちかけて来た時、自分に見せて来たのは何だったか。それはリストをスマホのカメラ機能で撮影したものだった。考えてみれば、単純だがおかしい。そのリストをゴルゴたちはどうやって入手したのか。
「フェイスブックをやってるやつから送られて来たんだ。出所は……知るもんか」
答えたのはラルフだった。
そのことに少なからずニッキーは衝撃を受ける。胸の奥に影が落ちてくるように、じわりと不安感が忍び寄って来たのだ。
ギルバードに怪しげな証拠を使って迫り、彼をエリスの殺害という罪を着せようとした。その企てにラルフは関わっていない、ゴルゴに担がれていただけなんだとニッキーは信じたかったのかもしれない。
しかし、ニッキーの願いは虚しく裏切られる形になった。
画像を入手したのはゴルゴではなく、自分の弟のラルフなのだ。
「どこの誰だか教えてみろ。そいつを警察に突き出してやる」
ギルバードは強い言葉を使って責めを続行する。
「知らねえよ。お前の噂をしてたら、いきなりメッセージで送られて来たんだよ。匿名でな」
それが苦しい嘘だということは、ニッキーにも分かった。フェイスブックは厳密に個人と結びついているので、「匿名」というのはあり得ない。必ずラルフはその画像の送り主を知っている。知らなかったとしたら……ラルフが画像の持ち主ということになる。教師にしか閲覧できないリストをスマホで撮影したことになるのだ。
「そのリストをゴルゴも持っているな。出所は問わん。二人でそれを見せてみろ。ここで見比べるんだ」
渋々といった形でラルフはスマホをいじると、例のリストの画像を表示させる。ゴルゴも同じようにしていた。
「同じだ。同じだぞ」
まるで助けを懇願するかのようなニッキーの声であった。頼むからラルフは許してやってくれと願うように言う。
「いや、違うな。この二枚はまるで異なっている」
ギルバードは毅然と言い放った。
そして、ゴルゴの方のスマホの画面に指を当てると、素早く下にスクロールした。
画面には給費学生に選ばれた五人と、その下の順位にいるギルバードの名前が出ていた。スクロールした先には、さらに先の人物の名前が出ている。
同じようにギルバードはラルフのスマホでもスクロールを試してみるが、画面はそれ以上下には行かなかった。
「は?」
ニッキーは拍子抜けしたような声を出す。
二人の持っている画像は別のものなのだ。ギルバードは頷いて、ゴルゴのスマホのリスト画面を指差していた。その先には成績が五位までの給費学生と、六位のギルバードの名前。そして、彼の指の先で信じがたい名前を見つけるのだった。
七位、ゴルゴ・アトランティック。
ラルフに送られたという画像は、うまく画面の下で切り取られており、不自然なアスペクト比でありながら、まるで「そこで画像が終わっている」ように偽装されているのだった。
最初にラルフから画像を見せられた時、それは最初から編集されているものだと思っていた。
だが、実際にその画像をいじったのは、ゴルゴだったのだ。
ゴルゴがスマホに保存していた、給費生リストの写真。これこそがゴルゴに確かに犯行の動機があるとする「確実な」証拠であった。
「この二枚の画像。オリジナルは……ゴルゴの方だな。言うまでも無いか。元のデータを持っているのがゴルゴで、それを改変したものをラルフは掴まされた。それでこの俺をエリス殺害の犯人だと思い込んだわけだ」
ギルバードは早口で告げて二人の顔を覗き込んでいた。
すっかり威勢の良かったゴルゴはなりを潜めてしまい、ばつの悪そうな表情を浮かべていた。ちらちらとそんな彼の顔をラルフは眺めている。
お互いに何かを考えているようだった。
(きっとこいつらは、この状況をひっくり返すだけの無実の証明をするんだ。その為に何を仕掛けようって言うんだ)
まるで夜が明けてしまうのではないかと感じられるほどの間が空いてから、ゴルゴの慎重に言葉を選んだ発言が夜闇の中に溶け込んでいった。
「ならよお……ロープがどこにあるか。分かってるのか?」
一瞬、ロープという単語が何を意味するのか理解できなかった。その正体を思い出す。
ゴルゴが先ほどの図書室での推理の中で、エリスを殺害した手段として、本棚をドミノ倒しにしたトリックとして使われたであろう道具だった。
まだ発見はされていないが、もしもそれがギルバードの元から見つかれば、それが物証となってこの状況を逆転することが可能だろう。
ニッキーはロープの存在を思い出したところで、これからゴルゴやラルフが何を企んでいるのか理解できてしまった。
(こいつら……唯一の物証になりえるだろうロープをどうにかしてギルバードの元に押しつけるつもりなんだ。あるいは、最初から彼へのとどめとして、そんな計画をしていたに違いない)
そんな危機に気がつけたのだが、ギルバードはそんな危惧をしているのかしていないのか軽い口調で答えていた。
「そんなものは警察が見つけるだろう。時間の無駄だ。とにかく今すぐお前達を通報して調べてもらう。そうなれば、ロープの在処なんて一瞬で分かるんじゃないか」
(駄目だ。時間を与えてはいけないんだ)
ニッキーは自分の心の中で叫ぶだけで言葉には出来なかった。怖じ気づいてしまったというのもある。彼の視界の中に存在していた上下二本の黒い線は消えてしまっている。すなわち、もうニッキーはこの場の主役ではあり得ないのだ。また観客へと戻ってしまっていた。
「ははは。そいつは結構だ。それならさっさと電話でも何でもしてくれよ、なあ」
ゴルゴはすっかり調子を取り戻してしまっている。
時間さえ与えらればどうにでもできるという自信がありありと見えた。
ギルバードに罪をなすりつけなくても、証拠を隠滅してしまえば逃げ切れるだろう。考えてみればそちらの選択肢の方が安全である気もした。ゴルゴはこの場を乗り切れれば、いくらでも打つ手があると考えているのだろう。
「それなら、この場は俺の嫌疑が晴れたということで、ひとまず終わりにしてしまうか。あとは警察が決着してくれる。他に誰も何も言うことが無ければ、帰らせてもらおう」
本気でギルバードは帰ろうとしているようだった。
一瞬、彼の視線がニッキーに向けられた。時間にすれば二三秒もなかっただろう。
このまま解散させてはいけない。ニッキーは拳を握りしめてそんな使命感に駆られるようになっていった。
でも、もう自分が抱いている違和感は存在しない。胸の中で淀んでいる記憶の吹き溜まりは、全て綺麗に取り除かれてしまっている。
(はったりでも何でも良いんだ……何か……何か)
ニッキーは焦りながら考え続けるが、さび付いたように頭は回らなかった。その代わりに気づいたことがあった。ギルバードの右手のストップウォッチはまだ押されていない。押そうという気配さえない。それが意味するのはすなわち、「まだこの場は閉じられるべきではない」という合図なのだ。ニッキーは数秒前に向けられた視線を思い出す。
(俺に送られていたのは、期待なのか?)
だが、いくら期待を寄せられても自分には何もない。ニッキーは首を振ろうとした。
(第一だな、俺は現場に居なかったんだ。そんな俺に何かを求めようなんて筋違いじゃないのか。現場の状況だってそんなに知っている訳じゃないんだぜ)
そうニッキーは不平を渦巻かせていたところに閃きが生じた。
(……待てよ……?)
口元を押さえながら目を開けたままで意識を過去へと持っていった。呼吸がゆっくりになって、そしてやがて記憶の中に一瞬で没入する。
過去に上映されていた映画のシーンを突然思い出してしまうが如く、映像がしっかりと蘇るのだった。
「あの時」
議論が萎みかけていたその場へ、まるで水滴が一粒垂らされたかのように、静かな一言が加えられた。
「俺の教室は図書室の近くにあったんだ。それで大きな音を聞いて……外に出た。何が起きたのか確かめようとしたら、図書館のガラスを本棚が突き破っていて、ガラスが飛び散って散乱していて、それで、俺は気が動転して……もしかしたらこいつが、弟が事故に巻き込まれたんじゃないかって現場に近づいたんだ。そしたら……」
ニッキーはそこで言葉を切ると、ゴルゴの方を見た。
「ゴルゴが話しかけてきたんだ。事故の状況を俺に知らせてくれた。一番に外に居て……誰もまだ避難していないような時に……集まってきた教師たちに紛れて、俺の方に来たんだ」
あの時、事件が発生した瞬間、もう授業終了のベルが鳴りそうだった。そこに巨大な音を聞いてニッキーは飛び出したのだった。
そして、一番に彼に状況を教えてくれたのは、誰だったか。
何故か廊下にいたゴルゴではなかったか?
それが意味するのは、すなわち……。
「お前、どうしてあの時に廊下に居たんだ。まだ事故が起きて一分と経っていなかった。そうだ、それはまだ授業の終わるベルが鳴っていなかった。鳴る前にお前は現れたろ。つまり、授業中にお前は『廊下に出ていた』ということになる」
つまりそれは、ゴルゴが図書館で本棚が倒れる際に「廊下にいた」ということを意味している。
「そして、もう一つ……。お前の制服は一つも傷ついていなかった。ラルフは壊れた扉から救出されたから肩のところが少し破れていた。しかし、ゴルゴには傷一つとして無かった。それにあの時、救急隊員からオレンジ色のタオルをもらって体にかけていたな。あれは……その制服の傷が存在しないことを隠すためじゃなかったのか?」
ニッキーが目を逸らし告げる事実に、ゴルゴは目を丸くして聞き入っていた。その二人が事件発生時に出会っていたのを、ラルフも見ていた。突然放たれたそんな言葉にラルフは何かを述べようとしていたが、下唇を噛んだだけで止めたらしい。
ゴルゴも抵抗の構えを見せようと辺りを睨み付けて思考を続けていたようだったが、ついには諦めたらしく、両手を広げて辺りをうろうろと歩き回り始めた。誰かに助けを求めるように天を仰いだり、頭を抱えたりしている。
電子音が暗闇の中で針を落とすようなささやかな響きを奏でる。
その方角をニッキーが見ると、ギルバードが右手のストップウォッチを停止させていた。
ブルックリンという街がニッキーは好きだった。
観光客がいたる場所でうろついており、そこに住む人間にとって心落ち着かない場合もあるが、それでも特別な時間は存在している。
日が暮れてきて観光客たちがホテルに帰り始める頃、人が引いていったこの街は何もかもが馴染みの「箱庭」のように感じていた。
かつてのブルックリンは工業都市として知られていた。
ニューヨークの労働者の集まる、観光とはまるで無縁の街であった。しかし、ここ最近は昔ながらのアメリカの暮らしを前面に押し出して、現代を生きるアメリカ人にとって馴染みのある街をテーマに景観を作り直した。
ニッキーは幼い頃から周りの大人達にブルックリンのあちこちで物語を聞かされてきた。
靴に用いられる革を加工していた工房と、そこに住んでいた可愛らしい娘。今、その娘はハリウッドで小さな劇場を沸かせる舞台役者となっており、小さな工房は人気のカフェになっている。
サーカスの小道具を専門に作っていた店は、いつ積まれたかも分からない煉瓦造り。ブルックリンの潮風に晒され続けたうっすらと白い壁が、陽の光で輝きを乱反射させる。今やそこはブルックリンの歴史を保存する記念館として観光ガイドにも載っている。
「なあ、兄貴。結局よ、皆この街が好きだったんだよな」
ニッキーはブルックリンの街並みが眺められる、川の近くの公園に来ていた。隣には弟のラルフがいる。
あれから事件は進展を迎えた。
エリスの殺人容疑がかけられたのはゴルゴであった。彼は職員室から給費生のリストを盗み出し、犯行を計画したのだった。特待生のエリス、そしてその次のギルバードがいなくなれば、給費学生として選ばれるのは自分だと考えていたらしい。
ゴルゴは警察に連行されていく前に、ニッキーとラルフにメールをくれた。
高校卒業と共にゴルゴはマサチューセッツに家族で移住することになっており、どうしてもこの街で一人暮らしをしたかったらしい。
それだけゴルゴはこのブルックリンを愛していたのだ。
しかしながら、ゴルゴの両親はキリスト教の熱心な信徒であり、自分たちに与えられた試練は、神からの贈り物なのだと信じていたようだ。
ゴルゴはメールで「そんなの冗談じゃねえぜ。実際は体よく工場を移転させるための前段階として先に営業所を作って、そこを起点に拠点を立ち上げようという会社の都合の良い理屈さ。親父達はそれを快諾したんだ。誰もやりたがらねえってだけでよ。『ニイちゃん』がよお、そう言ってるんだと。そうじゃねえだろ。あんたらを支配しているのは『ニイちゃん』じぇねえ。会社の上司と経営陣さ」と送ってきた。
いずれにしてもゴルゴは人を殺してしまった。
これからは一生をかけてその罪と向き合っていかなくてはならないだろう。
「ゴルゴの犯行に手を貸したのは、俺もこの街が好きで、俺とゴルゴと兄貴の三人でいつまでもこの街にいたかったからなんだぜ」
ラルフがゴルゴと共に行動をしていたのは、彼の事情を知って居ても立っても居られなくなったからだった。そういう意味で彼は共犯である。
警察はラルフの元にも近々やって来ると連絡してきた。逃亡の恐れはないので逮捕はしないという措置がなされたのだった。
だからこそ、こうしてブルックリンの街を眺めながら、二人でカフェイン入り清涼飲料をあおっていられるのだった。酸っぱいような苦いような後味に目元が細くなる。
「俺がお前の立場だったら、きっとそうしたぜ。俺だってゴルゴが好きだ。この街が好きだ。だから、きっと」
「いいや、兄貴は協力しないね。こんな事は間違ってるって俺たちを何とかして止めようとしただろうぜ。だから誘わなかったのさ、この共犯に」
ラルフにからかう様子は全くなく、誠実に意見を述べているようだった。
そんなことあるものかとニッキーは反論したかったが、実際、彼はゴルゴとラルフの犯罪をギルバードの言葉と共に暴いた。ラルフの言うことはあながち間違いでもないのかもしれない。
ギルバードは自分が犯人ではないにもかかわらず疑いをかけられていた訳だ。
どうして最初の段階で自分の無実を証明しなかったのかとニッキーは聞いた。
すると、ストップウォッチをスタートさせてから「警察も捜査に手間取っている案件に答えを出して、それで自分を犯人だと豪語してくる奴らは完全に怪しい。それくらい相手を疑う心がないとこれから先、騙され続けるぞ」と語ってカウントを止めていた。
要はギルバードはあの二人が自分をはめてくると予想した上で彼らの推理を聞き、全てがひっくり返る瞬間を待っていたそうなのだ。
全てがそれでは計算通りなのかと尋ねると、ギルバードは少しすました顔で言う。
「最後……最後の目撃証言だけは、計算外だったな。考えてみればお前のあの証言が決定打になった。フェイスブックで好きなだけ自慢すれば良いさ」
そんな憎まれ口を叩いてくるのだった。
ギルバードはこうして給費生としてブルックリンの大学に通い、この街に残り続ける。
最後に彼はこんなことを呟いていた。
「もしかしたら……非常に考えにくいことではあるが、もしも、もしものもしもの仮定の話をする。俺がゴルゴの立場だったら、人を殺すまではさすがに考えないが……何か普通ではない方法でこの場所に居残ろうとするだろう」
それはニッキーにとっても誰にとっても意外な「ゴルゴを擁護する言葉」だった。
「俺だってこの街が好きだ。給費生になれたのは、不謹慎だからあまり言わないが、素直に嬉しい」
ギルバードもまた、ブルックリンの住民なのだ。
…………。
…………。
「『ギルバードもまた、ブルックリンの住民なのだ』」
一人の男性がベッドの上でそう呟きながら、震える手で紙にそう書きつけていた。男は鉛筆を走らせるのも精一杯という様子で、自らの呟いた字を書き終えると、だらりとベッドの横に手を垂れさせた。
顔中を皺だらけにした老人が、小型のランタンの明かりだけを頼りに、暗くなった病室で、何やら書き物をしているようだった。
向かっているのは原稿用紙やノートではない。
彼が使う幅広の枕くらいのサイズをした、「漫画用」原稿用紙であった。
実際に枕元には何枚も同じような原稿が散らばっている。どれも完成はしておらず、鉛筆書きのままで放り出されているようであった。
今描いていたアメリカ、ニューヨーク州、ブルックリンの物語を締めくくると、散乱している紙の中に今の今まで手がけていた一枚を加えた。
「そろそろ、ああ……私の仕事も終わりか。稲妻のように駆け抜けたこの人生に、漫画があって良かった」
そのつぶやきと共にランタンの明かりが消え、老人は静かに目を閉じる。
平成最後の冬。
一人の老漫画家が、ペンを握ったまま大往生した。
幸いにして未完に終わった作品はなく、本人もかねてから「漫画を描きながら死にたい」という希望を述べておりそれが叶えられたことになる。
綺麗に終わらせたはずの彼の人生。
しかしながら、この後、一人の漫画家……一人の漫画家のアシスタントに大きな事件が降りかかることになるのだった。
おわり