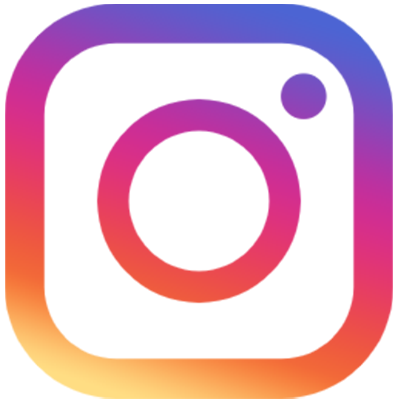毎月23日は小説の日!【アアルへの羽根(後編)】
僕の予感が的中しているかどうかは、これからの調査次第になる。
本棚にまずはファラオについて書かれた本をしまうと、この部屋に何が残されているのかを確かめようとした。
パソコンはもちろんなくなっており、書類も大半が持ち去られていると思われた。僕の脳裏には、よくテレビで見る光景が浮かぶ。段ボールを抱えて運び出している警察の姿だ。恐らくこの部屋にもすでに警察が入り、関係すると思われる資料は箱詰めされていったのだろう。
かつてパソコンがあったと思われるラックの横に、コルクボードがかかっていた。
そこには何枚かの紙が留めてある。
どうやら約束の時間をメモしたものや、今後の研究についての方向性、そして彼が大学で行う講義の予定などが書かれていた。
そこに気になるメモを見つけたので手にとってみる。
三月四日、面会。
几帳面な字でそう書かれていた。
面会か。そして、三月四日は鳩中ハヤタ氏が殺害された日だ。
部屋の真ん中に僕は椅子を持ってきて座ると、足を組んで唸った。
鳩中ハヤタ氏の殺害の日、芹沢雅氏は誰かと会う約束をしていたらしい。
面会という単語から思い浮かぶのは刑務所と病院だ。あの安生は留置所にいたらしいが、果たして留置所に面会という仕組みはあるのだろうか。
いや、弁護士以外は確か接触できないはずだ。
となると、芹沢雅は誰に会っていたのだ。鳩中ハヤタ氏が殺害された時に誰に面会をしていた。
そんな風に考えていると、いきなり部屋の扉がノックされた。こちらの返事を待つことなく、事務員らしき女性が扉を半開きにしてこちらを覗くように姿を見せた。
「あ、あの……こちらに何か御用でしょうか? 学生さん? それならねえ、ここはちょっと入ってもらっては困るのよ」
僕はちらりとその女性の後ろを見た。何人かの学生がその後ろについて、何やら耳打ちをしあっていた。
こんな状況にあってもなお、僕は冷静だった。
弁解はせずにただ「迷ってしまったみたいです。研究室を間違えましたね」と作り笑いをして素早く扉から出ると、加えて「早く行かないと教授に怒られてしまいますね」と人懐っこさを前面に展開して足早に去っていった。
それから研究室の並ぶ廊下に監視カメラがないことを確認すると、その足で図書館へと向かった。
監視カメラはあるかどうか遠目で確認をして、見当たらないようだったのでそこには寄らない。もしも見つかれば、立ち寄った記録は残しておく必要があったのだが。
不審に思われぬように大学を出る。
危ないところだった。
あの様子では学生たちにどうやら警備の人か警察を呼ばれていたようだな。あの場であと少しでも居座っていたら、危ないところだった。
だが、ここに来られたのは収穫だった。僕の中に一つの閃きが生まれ、それを確かめるための推理が始められそうだったからだ。
そのためにまず大切なのは「アアルへの羽根」の犯行文だ。
「『メンカラーは星の森への散策を計画するうちに罪を暴かれる』」
僕は芹沢氏の大学の最寄り駅から電車に乗って、スマホを覗いてその文章を軽く口に出してみた。
勘が正しければ、この一文は成立していないことになるのだ。それをまずは確かめるために文章を読み解かなくてはならない。
星の森への探索……。
鳩中ハヤタ氏の時のようにこれは死の状況を物語っているはずなのだ。ワイドショーによると芹沢氏が亡くなったのは心不全によるもので、自宅で料理をしている途中に倒れたとのことだった。
星の森と関係のあるものはあるだろうか。
しかし、何も考える材料がないので僕は一度電車を乗り換えて、自分の家の最寄り駅にたどり着いたところで何も思い浮かばなかった。
改札を出ようとしたところでパスケースを取り出すと、僕はポケットに何か引っかかるものを感じ取って、それを引っ張り出した。
カササギのキーホルダーがついた鍵だ。これは鳩中から受け取った、彼女の家の合い鍵だった。
「しまった」
昨日、鳩中に牛丼を買ってくる時に出入りが不便だろうと貸してもらったものだった。返却するのを忘れていた。
厄介なことになる前に返しておこうと僕は再び駅のホームに向かって、鳩中の家へと向かう。
何度も見ている棺桶型の家だが、少しも慣れるということはない。不気味さに目を細めてしまう。すると、家の門の前で誰かが立っているのが見えた。安生だろうかと警戒するが、見た目はもっと若く四十歳くらいの男で何度もインターフォンを鳴らしているようだった。
僕が近づいていくと、男は頭をかきながら一歩後ろに下がった。特に何も言葉はない。僕から別段話しかけることもなかったので、家の敷居をまたぐと入口の郵便受けに鍵を突っ込んでそのまま外に出ていった。
そんな僕を男は無言で見つめている。警戒されているようだった。
僕は作り笑いをしてできるだけ有効的に話しかけてみた。
「留守でしたか。僕も何度か来てるんですがね、全く反応がないんですよ」
さらりと嘘をつくのも慣れてきた。
「いや……」
対して男の方は挙動不審のままで僕と鳩中の家を交互に見つめては、何か言いたげに押し黙るのだった。
「もしかしたら別のところに引っ越してるのかもしれないですよ」
「いや、その、それはない」
はっきりと言い切ると、彼は鳩中の家の二階の扉あたりを指差して告げた。
「最初のインターホン、鳴らした時、あそこから、女の子、姿を見せた。カーテンの隙間から覗いてた。間違いない」
僕はしばらく黙っていた。誰か待っている人がいたのだろうか。それとも、僕が鍵を返しに来たのを確認しようとしたのだろうか。
どちらにしても、このままインターフォンを鳴らし続けてしても効果がないことは分かっていた。どうせ警察を呼ばれて終わりだろう。そう考えるが、僕はふと気がついた。
どうして彼は鳩中の家を訪れる必要があったのだろうか。
彼女の家の訪問者と言えば真っ先に安生の顔が浮かぶ。もしかすると彼も事件に関係があるのかもしれない。
「ひょっとして鳩中さんにご用事があるのですか。僕は彼女と同じ大学に通っている、継野というものです。よろしければ、用件だけでも伝えましょうか?」
僕のその提案に男はたちまち顔色を変えるのだった。何をそこまで驚くことがあったのだろうかと、男の顔を見ながら何パターンも考えてみた。
すると、彼は僕の予想の全てから外れる反応を見せるのだった。
「継野……さん? 継野英雄先生の弟か? い、いや、こんなに若くはないな……?」
彼の口から出た「継野英雄」というのは、僕の祖父の名前だった。
まさかここで事件とは関係がないと思われていた、僕の祖父である継野英雄の名前が出て来るとは思わなかった。
ひとまずその場は離れることにして、僕らは駅前に戻ると落ち着いて話せる場所を探した。
「科学カフェ」という古びた看板の店が目につき、男はそこを指差した。店内には人の姿がない。入りにくさから頭を振って、聞かれたくない話をするのだからなるべく人の多いチェーン店で人に紛れた方がいいと考えるが、スマホで調べるとここにはチェーン系の喫茶店が一つもない。
仕方がないので僕はその「科学カフェ」に入ることにした。
中はいたって普通の喫茶店であり、インテリアにビーカーやフラスコ、人体模型に月球儀が並んでいた。ステンドグラスがカウンターの奥にはまっていて、それは月面着陸を今にも試みようとしているイーグル号であった。
コーヒーを二杯注文して窓際の席につく。早くもコーヒーが来る。無口そうな店主は奥に下がって行ってしまった。
僕は警戒してその店主の後ろ姿を目で追い、不審な動きがないと確認してから話を始める。
「僕は継野英雄の孫だ。祖父をご存知ですか」
まず僕が切り出すと、男は無言でコーヒーをすすって店内の内装をぼんやりと見つめていた。
こっちの話が届いていたのか不安になってくる。
「君の、おじいさん、僕の先生だった。大学時代の、研究室の、先生」
それだけの関係ではないだろう。僕はそう目で語りかけるが、男はきょとんとしている。何だか頭の回転が遅くていらいらしてくるぞ。
追加で言葉を付け足そうとすると、男は思い出したように話し始めた。
「俺、加賀。科学のカガ。イントネーション。加賀、よりも、科学のカガの方がいい」
だんだん会話がちぐはぐになってくる。
だが、ここでしびれを切らしてはこちらの負けだ。僕は彼をカガと呼ぶことにして、追加の質問を投げつけた。
「カガさんは祖父の研究を手伝っていたのか。ただ授業を受けていただけじゃなくて。僕も大学生だから分かる。今でも去年の化学の講義の教授の名前は覚えないし、意識しなければ忘れるはずだ。それにあなたはまだ若そうだが、大学を出てもう何年とかじゃない、何十年は経ってるはずだ。だとしたら、ますます祖父のことが記憶にあるのは何か特別な関係だったと考えるのが自然だな」
一気にしゃべり続けると、カガは目をぱちくりさせていた。
「えっと、俺、あ……う、その……」
しどろもどろでありながらも、何かを訴えようとしていた。その様子に僕はますます苛立ってくる。
「俺、君の、おじいさんにお世話になった……けど、もうついていけなくなって、やめさせてもらった」
「祖父は厳しい人だった。あなたがついていけなくなったんですか」
「どっちも。どっちもだ。先生の言う正しさが、俺には、正しいものと思えなくなった。そうとしか言えない……」
正しさが正しいものとは思えなくなった。
その一言が僕の頭の中で一つの記憶を引き起こそうとしていた。何かが引っかかる。忘れられない一言としてかつては保管していたが、恐らく十年ほど前から砂に埋もれるようにして消えていったのだろう。
僕の思い出の片鱗と共にあるのは、亡くなった両親だった。
「……思い出した。君は先生のお孫さんだ」
「そう自己紹介しませんでしたか」
「大きくなった。会ったのはまだ小学生の時だった。正直に言うと、その時の君のこと、思い出せないけど、話をした記憶は、ある」
「……いつだ。どこで、何の話をした。あなたが忘れていても僕はきっと覚えてるはずだ」
「う……あの時だよ……その、お葬式の時。君のご両親のお葬式で話をしたんだ。どんな話をしたかは、ごめんよ、覚えてない」
僕は記憶を辿ってみる。
もう十年ほど前になるが、僕の両親は事故で命を落としていた。二人の乗った車が高速道路の壁に衝突した、単独事故だった。ブレーキの跡がなかったので自殺を疑われはしたが、最終的な結論はドライバーの操作ミスということにされた。
「けれど、両親を失った君を、少なくとも悲しみから救ってあげようと、力を尽くしたつもりだ。側にいて、話を聞いた。君は話した。今の気持ちを、色々」
そう言われて思い出してみると、両親の葬儀の時に唯一自分が話した時の記憶が戻ってきた。
一つは葬儀の終わりに数人の親族へ挨拶をしたこと。そして、父の友人という人物と今後について話したことだ。
「あの時の人か。僕が話した内容は覚えてます。これから親戚の家に世話になることと、遺品の整理も彼らに任せてあること、警察はみんな親切にしてくれること。でも、あなたの言葉は一つも思い出せない」
自分の言葉が強がりでないことを主張するように、そしてそれを気取られないように言う。
カガさんは優しく僕を見つめることしかしなかった。
言葉尻からはちっとも迫力というものを感じることはなかったのだが、無言の彼からは僕を包み込むような雰囲気を感じていた。彼の人間的な大きさが押し寄せるように向かってきた。その波のような温かさに僕は彼に対して侮れないという感情を植え付けた。
「あなたは話を聞いただけだ。僕の中では、その言葉は生きていないし……両親が死んでからの僕は一人だった」
噛みしめるように呟いた言葉の裏に、苦い記憶を見つけていた。
僕は僕を引き取ってくれた親戚をどうしても本当の親と思えず、ただ彼らの言われるままに生きた。
どんな待遇も気づかいも僕にとっては体を痛めつける嵐のようだった。親戚夫婦は食事の時に僕を必ず食卓の中心に座らせて、そのスプーンやフォークの動きの一つ一つを監視するように見つめていた。何か不都合がないかに常に気を張っていたようで、僕が食事の手を止めただけで、まさにそれが何かの合図になっていると信じていたがごとく振る舞った。おかわりはいいのか、舌に合わなかったか、明日から量を少なくするかもしくは多くするか。
息苦しさを感じてそれが爆発する前に、僕は高校からバイトを始めて奨学金で大学に入った。親戚夫婦は残念がったが、三日三晩寝ないで考えた「これまで養ってくれたことに対するお礼の言葉」を述べると、涙を流しながら僕を世間へと離してくれた。
借りたアパートで最初に食べたコンビニ弁当の味は今でも覚えている。始めてものをよく噛んで食べることがおいしいと感じ、気づかずに流れた涙は手の甲で跳ねた。
そんな半生を思えば、僕の人生を切り開いてきた存在は僕だけだ。
このカガなんて人物が出てくる余地なんてないはずだった。
「君は、当時は思わなかったけど、やはりおじいさんに似ているな。う……その、何というか雰囲気がさ」
「ところで、その祖父の知り合いがどうして鳩中の家を訪れる?」
「鳩中は俺と研究室が同じだった仲だから……あいつが死んだこと、今も信じられない。でも、それよりあいつは奥さんを病気で亡くしてから、娘の心配ばかりしてた……だから、両親とも失った人には支えが必要だと思ったんだ」
話が見えてきた。
つまり、彼は鳩中に慰めの言葉をかけるために家の前に居たのだ。それはまるで、両親を亡くした僕と同じく、鳩中を慰めてやろうとしたかのようだった。
僕は鳩中と口論になったことを思い出した。
彼女は心に寂しさを抱えていて、胸の中に空いた空洞を何とかして欲しくて、僕に悲鳴のような本音を浴びせたのではないだろうか。
それをあっけなく撥ねつけてしまった。
あいつの気持ちなんて全然考えたこともなかった。
そんな風に沈んでいきそうな心を励ますのは、目の前にしている大いなる「謎」であった。
そうだ。僕は謎に引きつけられていたから、彼女の気持ちを見落としただけなんだ。全てはこれを解決した後でも遅くはないはずだ。
第一、言葉だけでの慰めなんて何の解決にもならないじゃないか。鳩中だって望んでいるのは、父親を殺した犯人……安生を何とかすることに決まっているのだから。
そのためには芹沢の研究室で得た閃きの裏付けをしなくてはならない。
思考を本題に戻すと、僕は眼前のカガさんさえも事件の手がかりになるのではないか、聞ける話は謎解きの道具として使えるのではないかと思うようになる。
「『メンカラーは星の森への散策を計画するうちに罪を暴かれる』
鎌をかけるように呟いてみた。
しかし、カガさんの反応は薄く、むしろ僕のその口調や態度の方に気を引かれたらしい。
「う……君はおじいさんによく似ているよ。その人を試すような目は、やはり、少し、昔を思い出すな」
苦しそうにカガさんは言った。相当、僕の祖父に苦手意識があるのだろう。
「『アアルへの羽根』は知っているよな。あれはきっと被害者の死の状況を告げていると思う。現に最初の犠牲者も、この文章を思わせる状況で亡くなっていた」
「そ、そうなると、二人目の芹沢さんも?」
「カガさんは……芹沢さんとお知り合いなのですか?」
「う……芹沢さんは俺の大学の先輩だよ。元々は別の研究室にいたんだけど、俺と入れ替わりで君のおじいさんの研究室に入ってきたんだ。どういう研究をしたかは分からないけど……あ、そう言えば芹沢さんとは研究室を去ってからも、ちょくちょく会っててね、つい先日も、えっと、こんなメールが来てて」
そう言うとカガさんはスマホを取り出して僕にある文を見せてくる。
『例の告発について聞いておいてもらいたいことがある。いつものバーで話そう。時間は追って連絡する。明日の夜ならどうだ?』
メールの日付を見ると三月の二日となっていた。翌日というのは三月三日のことだろう。
ここまでの芹沢さんのスケジュールを洗い直すと、四日は誰かとの面会があり、そしてその前の三日にはカガさんと何やら話をするための約束をしていたようだった。
「告発? 例の告発とは何だ?」
それはきっと答えにくいことだったのだろうが、きっと「聞かれたら、答えよう」とカガさんは決めていたように思える。
一度息を吸ったカガさんは、前のめりになって僕の顔を覗き込んできた。
「き、君の、おじいさんのことなんだ」
ぎこちなく言い放たれた言葉に僕は表情をなくしてしまっていた。
ここで僕の祖父が話題の中心に滑り込んでくるとは、予想もしていなかった。せいぜい、祖父は鳩中の父親と知り合いであって、僕がこの事件に関わるきっかけになった……というだけの存在だと思っていた。
それが、殺された芹沢さんも、鳩中さんも、犯人を名乗る安生も、目の前のカガさんも、一人の人物によって結ばれているように思われる。
僕の祖父はどうやらそんな人物らしかった。
「祖父とはさほど面識はないんだ。それに、両親が亡くなった時にも姿を見せなかった。研究が第一というより、そうすることが当然であるかのような生き方をしていた。本来なら、法律上は、僕は親戚に育てられるのではなく、祖父の元に向かうことになっているんだろう。でも、周りがそれを止めた。祖父からも申し入れはなかった。だから、僕は祖父については『そういう人なんだな』と理解してるさ」
それはつまり祖父についての「告発」を真正面から受け止める覚悟があると言っているのであり、カガさんもそれに気づいたようであった。
「繊維性の血栓生成剤。その研究開発に関わる告発だ。君のおじいさんが主導して行った研究、それは致死性の薬物、それも研究目的は人を殺害することそのものだった」
急にカガさんの口調が鋭くなった気がした。
これまでの何かに怯えているような様子から一変し、恐ろしいものに取り憑かれたと疑ってしまうほど瞳に力を宿していた。
「そんな研究目的があっていいのか」
「当初はマウスでの『血栓生成の経過を探る』という名目で行われていた動物実験だったんだ。だが、君のおじいさん、継野英雄さんは、どこからかデータを大量に持ち込んで、それを人体に対応できるように変えてしまった……」
僕は祖父が行なっていたおぞましい研究結果を知らされたことになるが、さほど衝撃はなかった。
あの人ならやりかねないと心のどこかで思っていたのだ。
「それが、つまり、『アアルへの羽根』という訳か。どうして安生がそれを持っていた」
僕がすかさず聞くと、カガさんは呆けたような顔を一瞬するが、すぐに事態を把握したようで頷いた。
「俺は恐ろしくなって途中から研究を放棄してしまったんだ。噂には聞いていたが、君のおじいさんが亡くなってからは研究は芹沢さんに引き継がれたと聞いたよ。安生さんもその『アアルへの羽根』の論文の共同執筆者になっていたはず。それで、これは芹沢さんから聞いたんだけど、君のおじいさんの研究室が解散した時に『アアルへの羽根』は安生さんが持ち出したらしいんだ」
「何のために……もしかして、研究成果を独占するために」
「俺はそう考えてる。芹沢さんは安生が『アアルへの羽根』を持っていることを危険視していた。だからこそ告発しようと、そう俺に持ちかけてきたんだ。だから、芹沢さんは殺されたんだと思う……けど」
「『けど』?」
「どうして安生が鳩中を殺したのかが分からない。鳩中は告発に関わっていなかったし、研究論文にも名前はなかった」
「鳩中さんとはどういう関係だった?」
「俺と鳩中は同期だった。君のおじいさんの研究室に入ったのは、マウスによる血栓生成実験の第一人者だったからだよ。だからこそ、君のおじいさんが研究の方針を変えてから、研究室を去ったんだ。俺よりも後のことだったけど。でも、芹沢さんが告発をするって提案した時、鳩中は『もうあの研究には関わりたくない』って断ったんだ」
鳩中さんには告発の意思がなかった。そして、研究とは無縁の暮らしをしたかった。
だとしたら、一番に殺される理由はあるのか。
僕は事件の全体図がさっぱり分からなくなってきてしまった。
とりあえずカガさんの連絡先を聞いて、喫茶店で別れることにする。僕の推理はまだ未完成で、これから練り上げなくてはならないからだ。
最後にこれからどうするのかとカガさんに問うと、鳩中の娘には嫌われているようなので、帰ることにすると答えてくれた。しかし、駅に着くと「寄るところがある」と小さな声で言って、そこで僕と別れたのだった。
興味本位でついて行くと、彼はパチンコ屋に入って行く。てっきり事件に関係がある行動をするのかと思っていたのだが、がっかりしてしまった。
そこで僕もどこかで考えをまとめようとしたのだが、パチンコ屋から離れたところで肩を叩かれた。
「ちょっとお話を聞かせてもらえるかな。分かるよね。理由は分かっているよね」
僕に話しかけてきたのは、がたいのいい警官だった。
様々なことが頭を巡るけれども、抵抗をしても良いことは一つもないと判断して、大人しく言われる通りにすることにした。
てっきり留置所に連れていかれるものと思っていたが、警官に連れていかれたのは近くの交番だった。
「君、あの子の友達か何かなんだよね。それとも全くの見ず知らずの人だったりするのかな」
僕は警官と向かい合うようにして机に座り、彼の話を聞くに徹していた。
どうも、話を聞く限り、僕がここに連れて来られたのは芹沢さんの研究室に無断で入ったためでもなく、安生の一連の犯罪を知っているためでもないようだった。
素早く事態を理解した僕は、スマホを取り出すと、鳩中の番号を書き留めて連絡をするように頼んだ。
最初はにこやかだった警官は、やがて僕を怪訝な目で見つめるようになったが、僕の余裕ある対応に旗色が悪いと感じたのか、言う通りにしてくれた。
すると、問題はすぐに解決をする。
「本当に申し訳なかった。てっきり、インターホンをしつこく鳴らす男がいるという通報を受けて、現場に行ってみたら君の後ろ姿が見えたもので……それからしばらく辺りを捜索していたら同じ後ろ姿があったもので」
言い訳をしながら、警官は何度も頭を下げてくる。
「いえ、無実が証明されたのなら、それで良かったです。……彼女は何か話していましたか」
カガさんがしつこく家の前にいて、とうとう鳩中は限界を迎えたのだろう。僕が鍵を返しに言ったのとほぼ同じ時間に、彼女は警察へ通報をしたようだった。それから僕らは「科学カフェ」へと移動したので捕まらなかったが、警官はそれからも捜索を続けて、発見した僕だけを捕まえたという訳だ。
その誤解を鳩中自身に解いてもらい、僕は疑いを晴らすことができた。
「すまなかったと伝えてくれと。それだけだったね」
それもそうか。何か伝えたいことがあれば、電話をしてくるだろうからな。
そうして僕は交番から去ろうとしていたのだが、一つ気になっていたことがあったので、この機会に尋ねてみることにする。
「留置所にいる人に面会できるのは、弁護士だけですよね。警察で他に『面会』という言葉を使うことはありますか」
「そうだなあ。基本的には刑務所で刑に服している人に会うことを『面会』と言うけれど、その他となると……ううむ」
普通ならばここでこの謎を「世間話の一環」と捉えて、解決しないまま僕を帰してしまいそうなものだったが、彼は違った。
必死に頭をひねって答えを導き出そうとしている。
そして、彼の口から出てきたのは、僕にとって思いもよらないものだった。
鳩中が安生から言い渡された期間は、残り一日。明日が終われば彼は再び鳩中の家へとやって来て、答えを要求してくることだろう。全ての財産を自分に渡す覚悟はできたかどうか、と。
僕はその日は朝から家にいて、これまで調べた事柄をパソコンに打ち込んでいた。
一つの情報を打ち込むと、それがカードのように表示されて画面の上端に並んでいく。カード一枚につき、情報は一つ。
一通りカードを作成し終えると、マウスを使ってそれらを移動させながら思考を巡らせていく。
問題はただ一つ。
「アアルの羽根」の犯行文を送った人間は、本当にこの連続殺人を成立させているのか。
僕は「アアルの羽根」と書かれたカードを中央に持ってくる。
この文章によれば、「アアルの羽根」と呼ばれた薬剤によって三名の殺害が予告されている。
そのうちの一人は鳩中ハヤタ氏。
二人目は芹沢雅氏。
そして、三人目は鳩中史恵だろう。
一人目と二人目の殺害はすでに行われ、三人目の鳩中史恵は殺害予告をされている。
その犯人について。
これが奇妙な点だ。すでに安生という男が犯行を認めて、僕と鳩中の前に姿を見せているのだ。
それならばもう事件は解決しているのではないか。安生を警察に引き渡しておしまいだ。
だが、この安生には絶対的なアリバイがある。一人目の鳩中ハヤタ氏が殺害された時、彼は警察に拘留されていたと言うのだ。その証拠に、留置所で発行される書類を彼は持っていた。そして、鳩中ハヤタ氏の殺害された日と、留置所に安生がいた日は一致する。
故に、安生は鳩中ハヤタを殺害していないことになる。
これが最大の謎なのだ。
僕はカードを操作して安生のものと鳩中ハヤタのを並べてみた。
そうなると、どういう可能性が残るのだろう。
本当は安生は誰も殺していない、というのがまず候補に入ってくる。その説を裏付けるためには、それでは他に誰がやったのかという「真犯人」を見つけなくてはならない。他に「アアルの羽根」を持っていて、殺人の動機がある人物……。
真っ先に浮かんだのはカガさんの顔だった。
研究室が同じ彼ならばアアルの羽根を持っていてもおかしくはない。
しかし、彼に絶対的に足らないのは「動機」であった。それにもしカガさんが真犯人なら、犯人を名乗った安生を野放しにはしていないだろう。
あの犯行文を作ったのだとしたら、なおさらだ。
誰だって自分の犯行文を使われることは屈辱であるし、美しい悪の形から外れてしまう。
そんなことを考えていると、ふと僕の頭に気になる言葉が残っているのを感じた。
他人の犯行文を代わりに実行する……?
そして、芹沢さんの研究室で得た閃き。
僕はマウスを激しく動かしてカードを並べ替えていく。もしも、僕のこの推理が正しいのならば、この事件は奇妙なねじれを脱する。
その後に現れるのは、犯行文の輝かしい姿。
そして、この事件を綺麗に閉じる唯一の方法だった。
何のためらいもなく、僕はカードを移動させてみた。そして、幾度も自分の推理に穴がないかを確認している。それはまるで出来上がったばかりの楽譜に沿って、何度も何度も楽器を奏でて修練を重ねるようなものだった。
解明できた謎にうっとりして、そのまま僕は部屋のカーテンの隙間から朝日が差し込むのに気がつく。
約束の日がやって来た。
歓迎されないことは分かっていたつもりだが、それでも少しでも柔らかな表情を見せて欲しいと考えるのは自然なことだと思う。
僕はいつものカッターシャツにチノパンというラフな格好で、鳩中の家にやって来ていた。
できるなら安生よりも早く着いていたかったので午前中にインターホンを鳴らす。
しばらく無反応が続いたので、もし拒否されていて部屋に入れなかったらどうしようかと考えていると、何か布が飛んだかのように二階のカーテンが素早く開閉するのを目撃した。
きょとんとして待っていると、半分だけ扉が開く。
やれやれと思いながら敷居をまたいで近づいていき、中を覗き込むと、鳩中がそこにいた。目を逸らしている。その瞳は震えて弱っていた。心なし彼女がとても小さく見えた。痩せたんじゃないのか。
「分かったんだ。分かったんだよ、あいつの張った謎がさ。聞きたいだろ? 聞かせてやるよ」
僕は不敵に笑いながら言うと、病的に手を震わせて鳩中は僕の胸の辺りを拳骨で小突こうとしてくる。
「分かりましたよ、そして、もう……諦めました」
「何だと、そっちも謎に終止符を打ったのか」
「いえ、あなたに人間らしさを期待するのはもう無駄だと感じましたので」
「人間らしさ……。そんなことを気にしてたのかよ。こっちはあれから恐るべき謎に挑んで、大学に忍び込んだり、危険な目にあってきたってのによ」
それを聞くと鳩中はがっくりと肩を落とす。
「敵いませんよ、あなたには」
そんなやり取りの後で迎え入れられた僕は、部屋が散らかっているのに気づいたが、そのままにして机に座り、来客を待った。
のたのたと鳩中は部屋の整理を始める。何を今更という視線を送っていたが、こちらも立ち上がって台所でお茶をいれ始めた。
「客にはもてなしの心が大切だろ?」
「あんな人、客でも何でもないですよ。……それより、私はこれからどうすればいいんです。全財産を諦めて、どうやって生きていけばいいんでしょうか。そんなにあなたが考えるのを好むなら、考えさせてあげましょうか?」
「……そうだな。確かにそこまでは考えてなかったが、頭の中には少しだけ思いつきのようなものだけがある」
「それだけでも感謝します。それを話しておいてもらえると、助かると感じる人がいるかも知れませんよ」
答えようとしたところでインターホンが鳴り響いた。僕らは顔を見合わせて、ついにその時がやって来たのを悟るのだった。
「おやおや、少しお痩せになったのではないですかなあ。ちゃんと食べておられますかな」
三日ぶりに姿を見せた安生は、にこやかに鳩中を気遣っていた。第一、彼女が心を病む原因を作っているのは他ならぬこいつなだけに、気に入らないとは思うが口にはしない。
僕がいれたコーヒーの前に座る。同じように僕らの席にも一つ一つ同じものがあった。
湯気の立つそれらをじっと安生は見つめている。
砂糖かミルクが要るのかと思っていると、案の定、胃が弱いのと苦いのが嫌いといういかにもな理由をつけて僕を台所へと向かわせた。
「ああ、それと食後の薬を飲むのを忘れていましたなあ。水をいただけますかな」
それを僕ではなくて鳩中に頼んでいた。
望むものが食卓に揃うと、安生は錠剤を飲み下して僕らの方を見た。
「サインの方、していただけますかなあ。何、私もこの先、幾ばくもないでしょう。ただ有意義に日々を過ごしたいだけなのですよ。数年後に死んでしまったら財産のほとんどはお返ししますから」
その言葉はもう鳩中からサインをしてもらったという前提から吐き出されたものだった。僕は哀れみの視線を向けたまま言い放つ。
「残念だけれど、あんたはここにいるべきじゃない。すぐさま姿を消せば、今ならまだ間に合うぜ。幾ばくもないとか言ってるその余生、刑務所で過ごすのも良いんじゃないか」
「ほうほう。そこまで仰るのならば何か見つけましたかなあ」
まだ安生の顔は余裕に満ちている。作り物の仮面のように笑顔で綺麗に皺を作っていた。
再び机についた僕と鳩中を期待を込めた目で見てきている。
「まず、大きなところから話すぞ。この『アアルの羽根』という犯行文を用いた連続殺人事件、残念だけれどこれは連続して殺人が起きてはいるが、『連続殺人』として扱うにはちょっと不適切なんだ」
机の上で手を組んで、ジェスチャーは交えずに動きも少なめにして伝える。
僅かに僕の隣の鳩中が肩を跳ねさせて、驚いたような顔をしていた。
「連続殺人ってのは、同じ人物が連続して殺人を行うことだ。その定義が正しいならこの事件は連続殺人じゃない」
「そ、それでは犯人がもう一人居ると言うことになるのですか……?」
鳩中は弱々しい声で言う。三日は引きこもっていたし、元々大きな声で話すような性分ではなかったようなので、彼女の声量は心許ない。
「正確に言った方が良い。犯人はもう一人『いた』んだ。過去形なんだよ」
「もしやと思いますが、もう亡くなっていると言いたいんです?」
「鳩中ハヤタ氏を殺害した犯人は、この小悪党じゃない。本物の悪党になりたかった男……芹沢雅氏だ」
物語を説明するように僕は真実を明かしていく。明確に僕の告げる事実こそが真相だと信じているので、そこに迷いは一グラムも存在していない。脳内を流れる物質の全てが自信を生成してくれているのが分かる。
ともすれば鼻息が荒くなってしまいそうな場面だったが、僕は慎んだ。
一方の安生は涼しい顔のままだった。コーヒーカップに手を付けてしばらく手元の辺りを見つめており、こちらがしばらく黙ると「どうぞ続けなさい」と促すのだった。
「鳩中ハヤタ氏が殺害されたのは三月四日だな。ここから順番に話すと、芹沢雅氏は『アアルの羽根』を用いて鳩中氏を殺害し、誰かに発見させた。それから遺体を確認しに行っているんだ。芹沢氏の研究室にはそれを裏付けるメモが見つかってる」
僕はスマホで撮った写真を表示させる。とっさに撮影しておいた、芹沢の机の横に貼りつけてあったメモが表示された。
「四日 面会」
素朴な筆致で書かれたそれを見せても、なお安生は動じていない。ただ、何にも反応していなかった。凍ったような顔で僕の話の行き先を見守っているようにも見えた。
「ここにある『面会』というのは、この頃、十八日まで留置所にいたあんたに会うためじゃない。自分が殺害した相手の様子を確かめるべく、鳩中氏の遺体に『面会』を求めていたんだ。ちょっと警察の世話になることをして、その時に聞いたんだが、『面会』という行為が一般的に使われているのは、病院と刑務所だ。留置所は弁護士と面会……これを『接見』というらしいが、どうもそのような痕跡はなかった。こうなれば、あとは分かるだろう? 彼は……芹沢さんは死体を確認しに行ったんだ。犯人が現場に戻るというのと同じだろうな。ただ、どうして犯人が現場に戻るという習性があるのかは分からないけどな」
僕には人の心の細やかな動きが分からない。
それでも、様々な本で述べられていることや、一つ一つの事件の足跡から「こうではないか」と予想することで、人間の気持ちというものが完全に理解したとは言えないものの、予測や推理はできるようになっている。
「大方、これから行おうとする連続殺人に必要な『アアルの羽根』が、完全な殺害を成したかどうか確かめたかったんだろう。ここで確信を得られなければ、続けて人を殺すことなんて出来はしない」
僕はとうとうと推理を続けた。父の死の真相が明らかになったからだろうか、鳩中が俯いて肩を震わせていた。
「そして、マスコミや各方面にメールを送りつけた。これがいわゆる『アアルの羽根』の本文になるんだ。もちろんそれは鳩中史恵……あんたの所にも届いてるはずだよな。宛先は海外のサーバーになっている」
そう指摘すると、初めて安生の口元がぴくりと動くのだった。
「そうですね。どうしても見たければお見せいたしますが、君の言うように宛先はよく分からない所からになっています」
鳩中の受け取ったメールの宛先には、海外のサーバーを経由して送られてきたものと分かるようなアドレスが見て取れた。
これが一つ目のほつれになっているのだが、今すぐにこれを突いて破くということはしない。
「メールを送ったのは五日になっている。安生が留置所に居る時にはもう送られていたんだよ。けど、メールの送信なんて時間指定を使えばいくらでも誤魔化せる。重要なのはアドレス。これを覚えておいてもらいたい」
僕は鳩中のスマホを返すと、さらに推理を続けた。
「次の殺人は三月十九日。芹沢雅氏が死亡した。この犯人こそが、あんただ。安生能景。あんたは芹沢の研究室を訪れて、そして彼から『アアルの羽根』を奪うと相手に服用させて殺害した。これで、犯行文の連続殺人を実行するのは、芹沢からあんたに移ったという訳だ」
「……面白い、面白い推理ではあるが、果たしてそれを証明するものはあるのかなあ」
「あんたは間違えたんだ。悪への敬意が足らなかった。おおよそこの犯行文の最初、鳩中ハヤタ氏が殺害されるという文章について、その意味は芹沢氏から聞いたんだろう。だから、第二の殺人についての記述が読み解けなかった。星の森への探索。これが何を意味するのか理解できないまま、芹沢を殺害してしまった。その点であんたは芹沢氏には到底及ばない小悪党さ」
「答えになっていませんなあ。証拠を、と言っているのですよ。芹沢を殺したという証拠がどこにもないではないですか」
「そういうところが小悪党なんだ。見つからなければ罪ではない。確かにそれはそうだ。だがな、本当の悪人というのは誰にも疑わせたら駄目なんだ。その点、僕があんたを疑った時点でこの犯罪は別に謎でもないただの茶番に変わった」
「何を仰っているのか分かりませんなあ」
「考えてもみろ。あんたをここで警察に突き出せば、あんたは芹沢氏の殺害について事情を聞かれるだろう。その時に、こういうことに答えられるか?」
だんだんと僕と安生とのやり取りが早くなってきている。相手も熱くなってきたのか、ここを訪れた時の挨拶で響かせた声のだいたい倍の声量で主張を続けていた。
「まずはその『アアルの羽根』。これの中身はどこかで捨てるとしても、その瓶に芹沢の指紋がついていないか? そして、犯行文を送信しようとした時、芹沢のパソコンを開いていないか。開いているならその日時が彼の死亡推定時刻より前なら疑われるのはあんただ。キーボードやマウス。これに指紋はついていないか? ついていたらもちろん疑われるな。手袋をして弄ったとしたら、キーボードには不自然に拭き取ったような跡が付くだろう。後から拭き取ったら、それは論外だ。芹沢氏の指紋がついていないのは何故か。疑われる。それから、キーボード以外にもパソコンのある机にあんたの腕の皮膚から採取されるDNAが見つかったら、それでもおしまいだ。パソコンがノート型なら、ディスプレイを折畳んだ時にその指紋にも気を遣ったか? どうだ? 全てに完璧を求めたと言えるか?」
何一つ参照せずにまくしたてる僕を、鳩中は目を丸くして見つめていた。
これら全ては僕の推理のみが導き出した単なるはったりにすぎない。もしも安生が完璧に行っていると答えたのならば推理の信頼性はがた落ちになる。
しかし、心配は杞憂だと分かった。
先ほど述べたどれかに安生は心当たりがあるらしく、落ち着かない態度を取り始めたのだ。挑戦的に僕を睨んでくる。
「そんな脅しのような主張に屈するとでもお思いかな? よろしい。それならば警察を呼びたまえ。全てに答えを出して、それから再び君たちの前に姿を見せてあげよう」
ゆったりと安生は立ち上がると、自分のスマホを懐から取り出して何やら操作をすると、僕の前に放りだした。
画面には「110」と表示されている。この画面から「通話」の文字をタップすれば、それで警察に繋がって安生を通報できるだろう。
僕はスマホを手に取ろうとした。注意深く安生の手元を確認しながらの行為だった。
すると、いきなり安生は手元にあった水入りのコップを掴もうとしてきた。
咄嗟に僕は手にしたスマホを投げつけて、安生の手首に命中させる。
鳩中の悲鳴が上がる中でガラスの割れる音がして、水が床に撒かれて、安生は手首を押さえて仰け反っていた。
「こうなることも全部分かってたさ。後はタイミングの問題だったんだ。その水の中に、溶け込ませてあるんだろ。『アアルの羽根』がよ。水溶性かどうかは知らないけど、もしも水の中に入っているんだったら血液に少しでも混ざる……特に目や唇、口内に僅かでも入れば即死だ。僕たちにその水がかかっただけで、もうこっちは即死だったのさ」
僕は鳩中に説明をしたつもりだったのだが、一瞬の出来事にまだ事情が飲み込めていないのか、虚ろな視線を向けて何度も瞬きを繰り返すだけだった。
「う……ぐっ……」
「あんたにはふさわしくないな。『アアルの羽根』。それにあんたが狙ったのは僕だったろう? そういうところも、駄目なんだよ」
ため息をつきながら僕は目の前にあったコーヒーを手にして、静かに煽るふりをしてから、まるで植物に水をまくかのようにゆったりと、コップの中身を安生に振りかけるのだった。
一言も発することなく、コーヒーを頭から浴びた彼は全身のけいれんを起こす。震えながら地面に倒れて、先ほど自分のぶちまけた水をトレンチコートで拭き取るようにもがき苦しんだ。喉の辺りを押さえてから激しく呼吸をしようとして、上下に頭を動かした。
そして、十秒ほどで動かなくなった。安生は死んでしまった。
「狙うなら僕じゃなくて、鳩中が正しいんだ。アアルへと至る審判の場で、芹沢に会って来い。答えはそこで聞けば良いだろうよ」
安生の死体に向けて僕ははなむけの言葉を発した。
そして、彼の死体に歩み寄って懐から「アアルの羽根」の入った小瓶を取り出すと、机に残っていた鳩中の分のコーヒーを手にとって流しに捨てて水で入念に洗い流す。
そのうちに鳩中はようやく眼前で起きたことに対して理解が追いついたのだろう。
「こ、殺したんですか? 君……人を、人を殺した?」
「そうだ。よく考えてみてくれ。こいつはこれから警察に行って、罪を償ったとしても、それは命によるものにはならないだろう。そして、いつかかならず刑務所から出てきて、再び君の命を狙う。僕も狙われるだろう」
「だから、殺した……?」
「合理的だろ。しかも、この『アアルの羽根』が使われたんだ。心臓発作としか扱われないだろう」
僕は綺麗にコップを掃除して並べると、近くの汚れた皿を手にとって洗剤でついでに洗い始めた。
「こまめに洗い物はしておいた方が良いぞ。溜めるとやる気がなくなるからな」
「……何で……そこまで、普通にしてられるんですか。君はどこかおかしいです。おかしい……」
「おかしくはないぞ。こいつは芹沢氏の美しい悪を穢したんだ。それだけの罪がある。いいか。最初に疑わしいと思ったのは、こいつがあの犯行文の三人のファラオについて『三人の男』と述べたところだ。ところが最後に出てきたネチェルカラーというファラオは、ニトクリスと同一視されるファラオ。女なんだ。つまり、芹沢氏が殺害しようとしていたのは、男、男、女の三人さ」
皿を洗い終えてティッシュで念のために手の水気を取ると、僕は自分のスマホから救急に通報をした。知り合いが尋ねてきたのだが苦しんで倒れたと説明すると、急行するという返事を得ることが出来た。
「僕は芹沢の研究室でファラオの本を見つけてその事実に気づいて、安生を疑った。あとは僕のスマホに送られてきたメールだ。僕のだけはどうしてか皆より遅れて配信されてきたんだ。それも、君のと同じ宛先からじゃない。ほら。これはフリーメールだ。どこかの使い捨てのアカウントから送ったんだろう。恐らくは足がつかないように芹沢氏のパソコンを使ってね。そして、犯行文の『アアルの羽根』もきっと芹沢氏のパソコンから削除したはずさ。だから、あの時、指紋の話をしていたんだ」
きっと安生は芹沢のパソコンを使用しているに決まっている。そんな推理が安生を揺さぶるハッタリを生んだのだ。
「こいつもよくこんなぽっちの理解で悪を名乗ろうとしたな。僕はその点、完全に解き明かしたさ。芹沢氏が本当に殺害したかったのは、カガと名乗っていた研究員。彼はパチンコが趣味だったからな、『星の森への探索』というのは、パチンコのことだろう。星が釘で、それが密集するのを森と例えたんだ。それに、最後に僕を殺害しようとしたのは、そして僕にメールをわざわざ送ったのは、僕が『呪われた血』だと考えたからだ。ちゃんとして欲しいよな。鳩中ハヤタを殺害したというヒントがあったのだから、その血縁と考えれば最後は鳩中史恵という推理くらい出来るだろうに」
僕は心の底から安生を蔑んで言うと、椅子に座ったまま動けなくなっている鳩中を見やった。
「これでこの事件は収束するだろ。半年もすれば落ち着くはずだ。それまで辛抱しろよ。じゃあな。まあ、元気でやってくれ」
それは僕の別れの言葉だった。
まだどこか現実に意識を戻していない鳩中を横目で見ると、僕は「アアルの羽根」を大切に懐にしまって彼女の家を後にした。遠くから救急車のサイレンが聞こえてくる。僕はそれを背に悠然と現場から離れていくのだった。
大学二回目の春は、結局訪れなかった。
あのアアルの羽根の事件の後、僕は大学を辞めていた。
本件を通じて僕は祖父の存在と、そして彼が行っていた研究についてを知ったのだ。それについてを知りたくなったし、受け継ぎたくもなったし、さらには祖父の人柄についても知りたくなっていた。
夏が近づいた頃、僕は関東圏から離れた山間の村を訪れていた。駅から一時間に一本しか出ていないバスを使い、古びた屋敷にたどり着く。
入口は朽ち果てており植物に覆われていたので、ここまでこっそりと運んできた鉈を使って道を切り開いて中に入る。そして、放置されていた書類の数々を手に入れた。
アアルの羽根は祖父の継野英雄が開発した生物兵器が元になっているようだった。
かつての世界大戦において、祖父は祖国の戦いが正義のものから悪のものへと定義づけされることにいついて、深い苦しみの中にいたらしい。
その末に到達したのが、絶対的な力である毒薬の開発だった。
あれから色々な大学を巡って、祖父の研究についてを追いかけていた。
祖父の足跡に一つ出会う度に、僕が求めていた悪が心の中に宿る様な気がして嬉しくなり、旅路はどれも楽しみになり、やめられなくなっていた。
僕はどうして悪に憧れていたのだろう。
子供の頃から正義の味方よりも、それと戦う悪の方に心を奪われていたのだろうか。
十年以来の謎を祖父の研究と、アアルの羽根の存在は明らかにしてくれていた。
悪とは力なのだ。
そして社会において悪が悪いものと同義で使われるのは、誰もが腕力や暴力によって全てを掴むような世界になればそれは社会として成り立つわけがないし、平穏な暮らしなど得られはしない。
けれども、本当にそうだろうか。
振り返って考えてみると、僕らは悪によって生かされている面が多い。悪漢に襲われずに済んでいるのは、警察という武装をした正義に守られているからだ。しかし、武装をした警官というのは力の象徴であり、それ自体が悪だと言える。
だからこそ、社会に悪を置き続けるというのは、個人もしくは社会によってその力を押さえ続けることで成り立っている。人はそれを正義と呼ぶのだ。
そして、祖父は力を追い求め続けた。
決して誰かの判断や抑圧によって「正義」として扱われることのない、純粋で本質的な「悪」の姿を。
僕はそんな彼の遺志を継いで、今、アアルの羽根を手にしている。
きっと幼い頃の僕は悪の中にある本当の力を見つめていたのだろう。
それは正義のヒーローによって倒されて、テレビの中では一週間も経てば忘れられてしまう存在であるにしてもだ。
勝利によって周囲からの賞賛を得る「力」を嫌い、自然界に咲く野花のような美しい「力」を好きになった。それがすなわち悪であったというだけなのだ。
僕はこれからどのように悪をなしていくのだろうか。
誰にも評価されず、そして誰からも評論されることのない力。それをどのように生かして生きていくべきなのか。
僕は悪として生きることをまだ始めたばかりだ。
「アアルの羽根」と題された本を閉じ、主人公の継野の独白に思いを寄せると、結局自分は彼の言うような「小悪党」でしかないのではないかという気分になってくる。
そこまで崇高な悪を胸に抱いているわけではないし、欲しているのも個人的な利益だけだ。
図書館で二冊の本を読んでから、雪が降り始めた外に出て帰宅の道につく。
長い石造りの階段を降りて横断歩道で信号待ちをしてから、ブルックリンの街並みを歩いて行く。ここは観光ガイドの本に「代表的なブルックリンの街」として写真が載ったこともあるほど、ブルックリンが詰まった場所なのだ。
自分にとっては子供の頃から見慣れた街並みを歩いて行く。
次第に図書館で読んだ本に対して自分なりの反論が思い浮かんできた。
別に個人的な欲のために生きても良いじゃないか、と。
それが正義だろうが悪だろうが、人間はその日を生きていく生き物だ。
そんな個々で事情も価値観も違う暮らしにおいて、悪だとか正義だとかいうのは、後から付けられるものに過ぎない。
そう考えると確かに勇気がわいてくる。
積もり始めた雪の中を急ぎ足で進んで行く。
来週は必ず決行しよう。
人生を賭けた、一世一代の大仕事を。
おわり