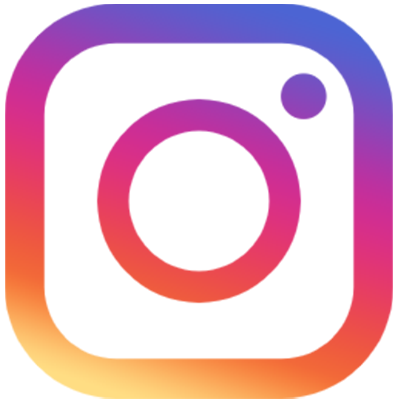毎月23日は小説の日!【アアルへの羽根(前編)】
心から悪人になりたかった。
大学に入る少し前から漠然と悪いことがしたくなった。それは犯罪に手を染めたり、反社会的な行為に荷担したりといったありきたりなものじゃない。
僕はそういうものとは一切かかわらない、本当の悪人になりたかったのだ。
そんな僕を変えるきっかけとなったのは、「アアルへの羽根」というタイトルのメールだった。
この一通のメールが僕の人生を、望んだとおりの悪の穴底へと突き落としてくれたのだった。
大学二年の春休み。
とある私立大学の薬学部に在籍する僕は、無事に二回生への進級を決めて、つかの間の一ヶ月程度の休みを謳歌するつもりだった。一回生の時は授業と課題でてんてこ舞いだったのだが、それも工夫すればかなりの時間を自分のために使えると分かったので、今年からはバイトを始めようとさえ思っていたところだった。
お金があれば覿面に(てきめん)活動範囲が広がるだろう。僕はサークルにも所属していなかったし、同じ学部内での交流にも何となく馴染めなかった。
講義を代返してもらったとか、試験でカンニングをしたとか、そういう上っ面だけの悪行を自慢するような同年代のやつらの輪にどうしても入れなかったのだ。
だからこそ、バイトによって自分の世界を広げようと思った。
世界を広げれば僕は本当の悪人になれるかもしれない。
本当の悪は何かを理解できるかもしれない。
そんな僕の状況をがらりと覿面に変えてしまう出来事があった。
それは同じ薬学部の一年生、鳩中史恵との出会いであった。
鳩中は学部の中ではあまり目立たない存在であり、というのも彼女は病気がちでなかなか大学の講義に顔を出すことが難しかったからだ。
数週間キャンパスに姿を現さないと思ったら、ひょっこり講堂の一番隅に座ってノートを取っているのを見かけたり、ふと大学内の図書館で本棚を眺めている姿に出くわしたりした。
そんな鳩中と僕は学部のはずれ者同士で覿面に気があった。
大学内で出会えばどちらともなくたわいのない話を始めたし、彼女が出られなかった講義のメモやレジュメをコピーして渡したりもしていた。
そして、出会ってから半年で僕は彼女の家に出入りするような間柄になっていた。
別にそれは僕が肉食系の男子だったからではない。どちらかと言えばこと恋愛に関して僕は奥手中の奥手であり、異性を前にすると頭の中にある言葉の七割がカットされてしまうようなチキンの中のチキンである。本当の悪人が聞いて呆れる。
そんな僕がどうして鳩中の家に上がりこめたのかというと、彼女の父親と僕の祖父が知り合いであったからだった。
「父が継野さんにお礼と、伝えたいことがあると言っていました。父は特に手土産などは気にしない人ですから、お気軽においで下さいませ。特に三洋堂の焼きプリン辺りが食べたい気分だと言っていたような気がしますが、それはそれとして、是非とも遊びに来て下さいね」
と、鳩中自身がその焼きプリンを所望しているのが丸わかりな発言をして、僕を家に誘ったのだ。
そして、僕……継野聡と鳩中との偶然の繋がりは、事態を奇妙な方向へと導く。これもまたきっかけは「アアルへの羽根」と題されたメールによってだった。
春休みも半分を過ぎた頃から徐々に昼間は気温も高くなってきて、コートも着ずに外を出歩けるようになってくる。僕はお昼時に原田屋の牛丼をテイクアウトで二つと味噌汁を持って、鳩中の家へと向かっていた。脱いだダッフルコートを片手に持っていると両手が塞がって窮屈だった。
鳩中の家はちょっと普通の家とは変わった作りをしていて、それも父親の趣味だということだが、二階建ての真っ黒い家であった。遠くから見ると巨大な棺桶のようにも見える。周囲の住人からは「不吉だ」と不気味がられているらしい。その棺桶に窓がいくつかはまっており、それが確認できるまで近づいた所でこれが「住宅」だと分かるのだった。
僕はその棺桶の家のインターフォンを鳴らして中に入っていく。
これで何度目だろうか。
初めて三洋堂の焼きプリンを半ば強要されるような形で持たされて、家に招き入れられた。それが僕の初めての訪問だった。そして今日は何日目になるのか。それさえ分からない。
「言われた通りに買ってきたぞ。原田屋の牛丼と味噌汁だ。冷めないうちに早く食おうぜ」
僕はリビングでテレビをかじりつくようにして見ていた鳩中に言う。
言葉をかけてから彼女は五六回ほどチャンネルを変えて番組を一秒ずつ観た後で、振り返るのだった。
「えっ、どうして私の食べたいものが分かったのですか? エスパーなんですか? 素晴らしい能力の持ち主ですね、継野さん」
「白々しいぜ。『原田屋の牛丼はチェーン店とは思えないおいしさなんですよね。証明できないのが残念です。ちょうどお昼時ですし、もしかしたら証明するのにうってつけかもしれませんね、お昼時でお腹も空いてきましたしね』とか言いやがって。買わせに行く気しかなかったじゃねえか」
「それはひどい誤解というものです。さては私たち、気が合いませんね?」
とか言いながら鳩中はビニールから牛丼を取り出すと、箸を割って食べ始める。僕もそれに続くのだが、彼女と自分の牛丼のサイズの違いを確認すると、改めて今がどういう状況にあるのかを気づかされるのだった。
僕の牛丼は大盛りサイズ。
そして、彼女の牛丼は普通盛り……のさらにそれを半分にしてもらった特注の「ちょびっと盛り」……をさらに半分にした「お淑やか盛り」であった。店員さんに無理を言って作ってもらった。
鳩中の食欲を考慮してのことだった。
あの日以来、彼女はずっと体調を崩したままだったし、食欲も「これでも普段の半分です」と言い張っていたが心配になるくらい少量しか食事を取れないほどに落ちていた。
僕と鳩中はほとんど同時に食事を終える。
そして、また彼女はテレビに向かうのだった。
一つのチャンネルに留まる時間はほとんど無い。いつでもリモコンを握りしめていて、しばらく時間が経つと次の番組に移動してしまう。
僕はそんな彼女の虚ろな横顔を眺めていた。
最初に会った時から病的なまでに色白だと思っていたが、ここ最近の心労でさらにその白さは増している。肩まで伸びているセミロングの髪の毛はくせっ毛なのか軽くウェーブしており、留めたり結んだりのアレンジは一切していない。最低限の身だしなみを整えるので精一杯なのだろう。
こうして僕が毎日訪れなかったら、どういう生活を送ることになるのか。
想像するだけであまり気分がいいものではないということが分かった。
彼女が心身ともに不調なのは、おおよそ半月前に起きた事件が原因だった。
その日はちょうど僕が初めて鳩中の家を訪れた日であった。
父に会わせたいという彼女の要望に応えるつもりだったのだが、肝心の彼が行方不明になってしまったのだ。
失踪する素振りはまるで感じられなかったというだけに鳩中の動揺は大きかった。
結局僕はその日、鳩中の父に会うことなくおいとますることになったのだった。
そして、行方不明になってから三日後、ふとバイト情報誌でも入手しようと出かける前に目にしたテレビで速報を見た。そこには白字の簡素なテロップでこう書かれていた。
「日本科学振興会会員 鳩中ハヤタ氏 遺体で発見される」
すぐさまその人物が鳩中の父だと分かった僕は、即座に彼女の元へ駆けつけたかったのだが、テレビではそれから鳩中ハヤタという人物についての説明を始めたので、そのまま番組に見入ってしまっていた。
日本科学振興会というのは、未来のノーベル賞研究者を育成するという目的で設立された会である。そこに集められた基金によって研究者たちは研究を進め、そしてその研究の成果を毎年、国民に向けて発表することになっている。
マスコミにも度々登用されてコメンテーターや事情通として出演することも多いので、日本科学振興会というのはお茶の間にも馴染みのある名だったのだ。
鳩中ハヤタは人工肺というものの研究で世界的に有名だったらしく、僕はその業績をテレビで初めて知ったのだった。
僕と会う予定だった人が亡くなった。
そのことで少なからずショックを受けはしたものの、だからと言って自分に出来ることは何もない。少なくともこれからしばらくは鳩中の家には立ち寄らないだろうし、もしかしたら彼女自身も大学に姿を見せにくくなるかもしれない。そう僕は鳩中ハヤタ氏の業績を称え上げて、この衝撃的な事件をひたすら取り上げるテレビのワイドショーを横目に見ながら、そう予想していたのだった。
一日経ち、二日が経ち、だんだんと鳩中ハヤタの死の真相がマスコミによって報じられるようになってきた。
警察の発表によって死因や死亡時の状況も分かるようになってきた。
ハヤタ氏は自身の研究室で椅子に座り、研究成果をまとめる論文の準備をしている最中に命を落としたらしい。部屋には荒らされた後もなければ争った形跡も微塵もない。まるで研究中にちょっと居眠りをしてしまったとでもとれるような状況だった。
しかし、そんな穏やかな現場でハヤタ氏は亡くなっていたのである。
死因は心不全だった。
心不全と言えば発作的に心臓が止まってしまうようなものと、血圧の上昇による慢性的なものの両方がある。僕も薬学部の学生なので一般に広く知られている病気のことは、一通り知識を持っていた。
そんな僕からしてみれば、死因が「心不全」というのは事実のみを公表しているに過ぎない。心不全というのはそもそも病名ではなく心臓の状況を説明する言葉なのだ。何らかの状況で心臓の働きが弱っていく、それをまとめて心不全と呼ぶのである。
問題は「どうして心不全になったのか」という原因の方だった。
しかし、そこは知りたくてもマスコミは教えてくれなかった。にもかかわらず、彼らはこの死を事件性のあるものとしてセンセーショナルに取り上げていた。誰々が氏を恨んでいたとか、トラブルがあったとかそんな話ばっかりだ。
体内からも毒物の反応はなかったとマスコミは発表しており、それから徐々に他殺の線は除かれていった。
ハヤタ氏の死は病死ではないか。
そんな風潮が出てきた頃、この事件は再び注目を集めることになるのだった。
別の研究員がまたもや「心不全」で亡くなった。
今度亡くなったのは芹沢雅という三十代の青年であり、やはり心不全が原因であった。この連続心不全といういかにも不自然な出来事をきっかけに、またしてもマスコミの報道は加熱していく。
そして、ちょうど芹沢氏が亡くなった次の日だった。
マスコミは朝から、テレビ局に送られてきたという「怪奇メール」の件で騒いでいた。何でも各局のメールフォームに謎の文面のメールが送られてきており、差出人の名が「鳩中氏と芹沢氏の関係者」とされていたことが彼らの興味をかき立てたのだろう。僕はその報道を「いたずらじゃないか」と冷めた目で見つめていたのだが、やがてそうも言っては居られなくなるのだった。
それと同じメールが僕のスマホにも送られてきたからだった。
文面はこうだった。
「アアルへの羽根
それは冥界への道しるべ
正しき者は永遠の楽園『アアル』へと至る権利を得る
重き者は第二の死を迎えることになる
羽根は心臓との重さ比べの審判に用いられる
罪とは無縁と信じる者よ
その胸を開き心臓を真実の天秤へとかけるがいい
アアルの羽根は逃すことなく汝の罪を暴く」
ここまでなら単なるいたずらだと一蹴してしまうだろう。しかし、問題はそれに続く文面だった。
「ラネブは秩序を神に願う時に罪を暴かれ
メンカラーは星の森への散策を計画するうちに罪を暴かれる
人は皆、罪の子である
ネチェルカラーは生まれの呪いによって裁きを受ける
誰もアアルに至ることなく
羽根の真実によって数々の罪は太陽神の元に晒される」
マスコミはこれを犯行予告ととったようだった。
このメールの後半に出てくる三つの名は、どれも古代エジプトのファラオの名である。中にはまだ功績も人柄も不明であって、名前だけが知られているというファラオもいた。
だが、このファラオの名は現在死亡している二人の研究者と「死亡の状況」が一致していると思われたのだ。
そうなってくると警察もマスコミも次に考えるのは「第三の被害者の警護」であった。予告文には三名の名が記されているが、最後のネチェルカラーという人物だけはまだ存命である。誰もがそう考えているようであった。
僕は世間がそんな推理をしている中、もう一つの謎に苛まれていた。
この予告メール「アアルへの羽根」がどうして僕の所にも届いている?
何か関係するところがあるというのだろうか。しばらく思索を巡らせてみると、最近告げられた事実を思い出すことになるのだった。
自分の祖父と、鳩中の父親は知り合いだったらしい。彼女はそう話していた。結局、どんな繋がりなのかは教えてもらっていないので分からなかった。
そして、鳩中の父親が死の直前に会いたがっていたのは自分だ。
それももしかしたらこの事件に関係しているのだろうか。
もちろん警察にも相談をしたが「考えすぎではないですか」と中年女性の警官に電話口で諭されてしまい、それでも「何がその後、変わったことが起きるようならば教えて下さい」と電話番号を控えられて電話を切られてしまったのであった。
もしかしたら、疑われたのかもしれない。
こうして事件と無関係の所に置かれたところで、改めて僕は岐路に立たされた。
このまま事件とは無関係を装って春休みを満喫し、バイトを探して大学生活の二年目に備えるべきか。
それともあくまでこの一件に首を突っ込み続けて、事件がどこに至るのかを見届けるべきなのか。
迷いに迷った僕は、送られてきた犯行メールを何度も何度も読み返していた。ネットにはマスコミがメールを公開したことによって、同じ文面がどこででも読めるようになっていた。掲示板では文面の考察も行われている。
別に僕だけがこの文章を読めるわけじゃないんだ。
だが、そう思ったところで一つだけ彼らと僕との違いを見つけ出すことが出来た。
犯人と思われる人物から直接メールを受け取っている。
どうして犯人らしき人物は僕のメールアドレスを知っているのか。そして、僕をこの事件に巻き込もうとしているのか。そんな考えはやがて犯人の心理状況にまで及んでいくことになる。それはつまり、どうして彼はこんなことをしようと思ったのか。どうやって殺したのか。何故殺したのか。いつ殺したのか。どこで殺したのか……。
悪人に僕は憧れていた。
それは僕の中の大きな謎の一つでもあった。どうして悪人なんかになりたいと思っているのだろうか。
どのような者が悪人かも分からぬまま、何故自分は憧れを抱いているというのか。
数々の疑問がもしかしたらこの事件を通して解決されるかも知れない。
そんな期待から、僕は鳩中の家に再度向かうことにしたのだった。この事件への入口は、恐らく鳩中の父親と僕の祖父との繋がりであると考えたからだった。
そうして僕は毎日鳩中の家に出入りし、彼女とこうして牛丼を食したり、父親のハヤタ氏の書斎を探って僕の祖父に繋がる何かを探したり、テレビで事件の進展を見守ったりしているのだった。
「今日のマスコミの話題はどこに集まっている? 昨日は芹沢さんの育った環境だったっけ」
僕は、高速でチャンネルを変えていく鳩中の背中に話しかけた。
「今日は犯行文の新しい解釈について。それから芹沢さんのご家族へのインタビュー。警察の見解について。観ていて全く飽きないですね。何時間も続く映画を見続けているような感じです」
こちらには目もくれずに答えた。
鳩中は事件が発生し、自分の父親が亡くなってからずっとこうしてテレビを観ている。何か真実に至る扉が液晶の向こうにあると信じ、ひたすら覗き込んでいる風さえあった。
その行為を僕は何とも思わない。
何かマスコミが新しい報告をすればすぐに教えてもらえるし、僕はそのお陰でこの鳩中家の家中を何の制限もなく捜査し続けられるのだから。
僕は鳩中に父の書斎を調べるよと一応断ってから、返事も聞かずにリビングから奥の部屋に移動していく。
鳩中氏の書斎だ。
多くの本や紙片が詰まったこの部屋はおおよそ一ヶ月や二ヶ月程度ではひっくり返せない。パソコンも置いてあり、その中身も調べるとなると膨大な時間がかかるのが分かった。
僕は今日も、何のためらいもなく鳩中氏のパソコンを立ち上げて調査を開始する。個人宛のメールはもうほとんど読んでしまっていた。
読めば読むほどに彼女の父親の性格が理解できてきたのだが、僕の知りたいこと、特に僕の祖父と彼との関係はどこにもそれをうかがわせるものがなかった。
どうしてこの人は僕と会いたがったのだろう。
進めば進むほど周りは明るくなっていくが、進むべき道もそれに続いて広がっていく。行き止まりはどこにも見えないのに行き詰まっていく感じがしていた。
これは解明には時間がかかりそうだと僕はため息をついてメールを閉じ、そしてパソコンをシャットダウンさせようとしたのだが、ふとあの例の「犯行予告文」を思い出してスマホを取り出す。
「『ラネブは秩序を神に願う時に罪を暴かれ……』」
その言葉を呟いてから思慮する。
ラネブというのは鳩中ハヤタ氏のことだろうか。まずそこから疑ってみるのもいいかもしれないが、一つ一つ考えていくとして、まずラネブをハヤタ氏と想定してみる。
秩序を神に願う……?
何のことだかさっぱり分からない。ネットの考察でもこのファラオの名と「罪を暴かれる」という行為については確たる答えは得られていない。
罪を暴かれるというのは恐らく「殺害される」の隠語だろう。それは分かるのだが、それぞれの言葉……秩序、神、願う……といったものが何を指し示すのか分かったものじゃない。
僕は近くにあった紙に鉛筆で「秩序、神、願う」と書き出してみた。それを窓の光にかざすようにして透かしてみる。しかし、特に何も新しい視点は生まれそうになかった。
インターフォンの音が聞こえた。
もしかしたら警察の人間が何か新たな情報を持ってきたのかも知れない。そう思ってリビングに戻ると、テレビがつけっぱなしになっており、その場から鳩中の姿が消えていた。
辺りをよく調べてみると、彼女は部屋の隅に移動してカーテンで身を隠すようにしている。
「お客さんだぞ。もしかしたら、事件について何か聞かせてくれる人が現れたのかもしれない。ほら、早く出なきゃ。留守だと思われて帰られてしまうぞ」
僕はそう言いながら鳩中の肩を掴んで立たせようとするのだが、その手は振り払われてしまった。何度も彼女は首を振る。そして、この事態から逃れようとするかのように耳を塞いで、その場から動かないと主張するように顔を伏せてしまった。
どうしてそんな態度を取るのかと首を傾げ、ここは僕が応対することにした。
僕も全くの無関係者という訳ではないので、警察から咎められることもないだろう。
そう思いながら玄関まで向かって扉を開ける。
僕が予想していたのは警察の制服を着た人か、スーツ姿の警官かのどちらかだった。しかし、目の前に現れたのはそのどちらでもない風貌の人物だった。
一目見て、ぞくりと背中を何か冷たい生き物が這い回ったような感覚になる。手に汗がにじんできた。
「鳩中史恵さんではありませんなあ。どうされましたかなあ。そちらはどなたですかね?」
本来なら「そちらはどなた」というのは僕の口から出てくるべき言葉なのだが、相手は何の臆面も無く言い放ってくるのだった。
シルクハットから覗く眼光は鋭く、眉毛もヒゲも全て白くなっていた。若干、背骨が曲がっているのか前傾姿勢になっているが、顔つきからはまるで老いを感じさせない。黒のトレンチコートを羽織ったやせ形の老人が一人で立っていた。
「どおれ、邪魔するよ。この件は春が終わるまでに片付けたいものだなあ。行楽シーズンが終わってしまうからのう」
まるで独り言のように言って、老人は僕を突き飛ばすように進んできた。
僕の姿など眼中にないと言わんばかりの行為に、つい驚いてしまって、後ろに仰け反ってしまった。
この老人は誰だ。
怪訝に思う気持ちと、いきなり体を押された不快感が混ざって顔に出てしまったのだろう。彼は僕をちらりと見ると僅かに口を歪めた。その態度には確かにムッとしてしまったが、突っかかっているような勇気もない。
もしかしたら、彼は警察の関係者かもしれないし、鳩中の親族の誰かである可能性もある。
そうでなければここまでずけずけと他人の家に入り込めるものでもない。
ゆっくりと老人は歩き、一歩一歩を踏みしめるように進んでいった。足でも悪いのだろうか。
そうしてリビングについた時、部屋の隅に鳩中を見つけて老人は言った。
「おや、随分と成長しているねえ。ハヤタくんから写真を見せられた時は、まだ幼稚園くらいだったからねえ。小学生ぐらいかと思ったんだけどねえ」
誰だ? という視線を鳩中に送るが、すっかり彼女は怯えたような顔をして首を振るだけだった。潤んだ瞳がこう訴えている。「そんな人は知らない。早く出て行ってもらって」と。
だが、俺はそんな彼女の表情を無視した。ソファーに座るように促して、自分もその対面に腰をかける。
「鳩中とその父親について知っているみたいだな。でも、警察やその関係者でもない。そして、鳩中とは面識はない。父親から写真を見せてもらっただけなんだろ。あんたは誰だ」
「なかなかに頭の回りがいいなあ。けれどな、そんなものは役には立たないのだよ。全ての出揃ったピースを繋げていく作業は、時間をかければ誰にだって出来るしなあ。どちらかというと、人間にとって大切なのは閃きを得る力だよ」
「質問に答えて欲しい。あんたは誰だ」
「君に警察は向かないなあ。探偵にもだ。もっと相手の話に乗るようにして聞き出さなければなあ。相手に警戒されては全てがふいになる」
僕は舌打ちをして、先ほどからうるさかったテレビをリモコンで消した。その時に放り投げた音で鳩中がびくりと肩を震わせるのが見える。
「警察を呼んでもいいんだぞ。僕は探偵にも警察にも向いていないかも知れないけど、電話をかけるくらいは出来るんだ」
「ま、それもいいかもなあ。好きにしたまえよ。パトカーが集まってくるのも久しぶりに見ることになるから、それも楽しみなんだ」
さっきからこの老人の話はのらりくらりとし過ぎていてちっとも前に進まない。しかし、それをボケていると感じさせないのは、彼の言葉の裏では論理の一貫性が乱れなく保たれているように感じるからだ。
「その前に、鳩中史恵さん。あなたに話がしたくてここまで来たんですな。お願いですから、この老人にお顔を見せて下され。ささ、こちらに来てソファに腰掛けてなあ」
半身をよじって老人は鳩中に呼びかけるのだった。まるで、善良な老人が孫に呼びかけるが如く言うのだった。
言葉の節々への甘さを感じ取ったのだろうか、鳩中は時間をかけて部屋の隅から立ち上がると、さっと僕の隣に座って、テレビのリモコンを取ると電源を付けた。またワイドショーの解説が聞こえてくる。
「耳障りなんだよ。この人との会話に集中しないか?」
「今、良い所なんですよ。コメンテーターに青森さんが居ますよね。フィギュアスケーターで哲学博士号を持っているんです。滑る哲学者なんて言われて。そんな人がこの事件をどう考えているか観てみたくないですか?」
別にどうでもいい。
「オリンピックにいつも出られなかったスケーターさんですなあ。でも、私は好きでしたよ。彼は滑ることについて本当の意味を知っているようだ」
まるで紙がしおれて折れるような速度で老人は笑みを作るのだった。
「スケーターは滑ることについての本当の意味を知るべきですなあ。そして、警察は事件についての本当の意味を知るべきで、八百屋は野菜を売ることの本当の意味を知らなければいけませんなあ」
「じゃあ、あんたは何について知るべきなんだ」
「なるほどなあ。今、初めてあなた、探偵っぽい質問をしましたねえ。嬉しいですよお。そうですねえ。私のような者が知るべきなのは」
そう言って老人は軽く髭を指の甲で撫でるのだった。
「悪について、知るべきなのでしょうなあ」
のたりのたりとした言葉だったが、僕の心の中に素早く放たれていった。「自分がこうあるべき」と書くだけ書いてみてどこにも張り出す場所のない、「心の方針」を老人の一言は貫いて壁にしっかりと留めるのだった。
僕は彼から学ぶべき事がある。
そう確信した時に思わず浮かんでしまった笑顔は、歓喜によるものではないと言いたい。
弛緩したのは気分の高揚によるものだ。
老人は再び点いたテレビの画面に視線をやっているようだったが、僕の表情に気がつくとバツの悪そうな笑みを曖昧に浮かべる。
「確かに気になる雑音が多いかもしれませんなあ。鳩中さんには少しだけ我慢していただきましょうかなあ」
そうのんびりとした口調で言うと、そっとリモコンを取ってテレビを消す。それから、鳩中にリモコンを手渡すのであった。
「すみませんなあ。すぐに終わる話ですのでその間、我慢してくださいなあ」
と言ってから鋭く僕を見据えた。
「ともあれ、その『すぐ』がどれだけの時間になるかは、鳩中さん次第ということになりますがなあ」
含みのある言い方だった。あくまで自分は何かを聞きに来たと言いたげだ。一方的に聞かせに来たのではないと。
だが、一体彼が何を聞こうとしているのか、どういう目的を持っているのかは依然として分からない。
これからどんな話が始まるのかと警戒していると、老人は思い出したように胸元のポケットを探る。
そして、一枚の紙片を取り出すのだった。
「もう飽き飽きするほどご覧になったと思いますがなあ。今一度、この文学的作品をどうぞ」
開かれたのはあの「アアルへの羽根」と題された犯行文であった。見たところ、僕が受け取ったメールのそれと違う部分は認められない。
「この文面に出てくる三人は、男のファラオなんですなあ。インターネットで調べれば、まあ明らかになることですがなあ。問題は、彼らがこの間から世間をお騒がせしている怪死についてを物語る、登場人物となっている点です」
老人は僅かに曲がった指で犯行文の「ラネブ」と書かれている部分を指した。
「ラネブは鳩中ハヤタさんですなあ。メールには秩序を神に願うと書いてありますが……ほう、あなたもそうして閃きを得ようとしていたのですなあ」
感心した声の老人の視線の先には、僕が先ほど書いたキーワードを列挙してある紙があった。
「さしずめ、閃きを諦めてしまったというところですかなあ。簡単なことですよ。ハヤタ氏の死の状況をその瞼の裏に浮かべれば良いのです」
優しげな口調でそう告げる老人は、さながら幼い子に勉強を教えているようであった。
「重なるでしょう。ハヤタ氏は論文の執筆作業中に亡くなった。それも、彼が本腰を入れて取り組んでいた人工肺の臨床データをまとめている時ですなあ。昨今では人工肺は拒絶反応を起こすやら、遺伝子工学そのものが人道的に誤っているので禁忌とするべきやら、様々な抵抗に遭われてきた。それがすなわち『混沌』。カオスという訳ですなあ」
髭を指で繰り返し整えながら言う。その動きが様になりすぎていて、まるでこうして僕らの前で披露するためだけに髭を生やしているのではとさえ思えた。
「カオスの対義語はコスモス。すなわち『秩序』ですなあ。ハヤタ氏は健気でした。世論という神に自らのコスモスを訴えるべく、苦労を重ねて……そして亡くなっていった。その働きは実に無常を表しますなあ」
その言葉と共に僕の隣で大きな音が聞こえるのだった。
「鳩中さん……」
拳を震わせて鳩中が立ち上がっていた。音は彼女が立った時に膝かどこかを机にぶつけた時のものなのだろう。
鳩中は勢いよくテレビのリモコンを掴んで、そのスイッチを入れた。そして、元の通り腰をかけると虚ろな瞳でワイドショーを見続けるのだった。
何だったんだ今の行動は。
そう思って鳩中の顔を見るが、いつものように表情はなかった。首を傾げていると老人が再び話し始めるのだった。
「怒っておるのですなあ。相当に彼女にはストレスがあるとお見受けしますが、君は一体どんな風に彼女と接していたのですか」
問われて思い返せば、僕は鳩中の気持ちを慮ったことなんてなかったのかもしれない。
ただ僕はこの事件が与えてくれる何かを探して、ひたすらに鳩中の父親の部屋を引っ掻き回していただけだ。
でもその無礼は彼女が欲しがるものを買ってきたことで埋め合せられていると思っていた。最初は焼きプリンから始まって肉まん、カップ焼きそば……そして今日の牛丼だ。
もしかしたら俺は彼女の気持ちを微塵も分かってなかったのか。
「いいですかな、鳩中さん。私はね、この男よりもあなたにこの話を聞かせたいんですよ。もう少し我慢していただきたい」
「わ、私は何も聞きたくはないです。でも、父が亡くなったことについてを、もしもどこかで話している人がいれば、少しは気持ちの整理もつくかもしれませんね」
いつものような控えめな注文だった。鳩中はこんな風に遠回しに告げるけれども、その本心は「父の死について知りたい」ということなのだろう。
「その言葉をお待ちしておりましたよ」
老人はそう言うと髭に手を当てて述べる。
「私こそがこの文章を作成した本人なのです」
その言葉を受け止め損ねてしまった。つるりと滑り落ちた老人の告白によって、僕は耳鳴りを起こす。
「この文章を書いて、マスコミと鳩中さんに送ったのは私です。意味がお分かりになりますかな」
優しげな笑みと共に老人は言う。くしゃりと現れる皺の一つ一つがまるで計算され尽くしたかのように美しい模様になって浮かび上がる。
文章には鳩中ハヤタ氏や芹沢氏の死の状況が書かれている。そして、それについてを克明に老人は「まるでその場にいたかのように」語っていたのだ。
すなわち、答えは一つだ。
「申し遅れましたなあ。とんだ無礼でございました。私は安生能景(あんじょうたかかげ)と申します。あなたのお父様を殺害し、もう一人の罪人も殺害し、そして、これからあなたを殺害する者でございます」
一字一句、安生と名乗る老人の言葉を、思い出せる範囲で再生してみた。
そうしているとゆっくり事実関係が胸の中に滴るようにして理解できてきた。
安生はこの「アアルへの羽根」という文章を書き、犯行に及んだ。
つまり、ありていに言えば、この事件の犯人なのだ。
表情が普段はほとんど変わらない鳩中だが、安生の言葉にはさすがに驚きを隠せないようだった。
しかもこいつは次に鳩中を殺害すると言ったのだ。
安生は胸のポケットから自然な動きで小瓶を取り出して、僕たちに見せてきた。
中には真っ白に揺らめく糸の塊のようなものが見えた。
「紹介しましょう。これが今、世間で話題になりきっている『アアルの羽根』です。薬学部に通うお二人ならば、薬剤というものは人体に効能をもたらすばかりでなく、時には悪なる影響も及ぼす。副作用というものですなあ。そして、薬剤はその副作用をなるべく抑えるようにしてデザインされていく」
僕は安生の話がどこか遠くでされているものだと思えてしまった。意識はそれ以上に、アアルの羽根、彼が今手にしている小瓶の中身に注がれていた。
美しいものにもおぞましいものにも見えなかった。ただ、視線を引き付けられてしまうのは、その白く扇型に広がった構造物が人を殺すのだという考えが、目の前の老人は人殺しであるという認識を確かなものにしたからだった。
アアルの羽根を取り出した安生は、先ほどよりも覿面に特別な存在に見える。
畏怖と憧憬とを対面する者に抱かせるような風格が彼には備わっていた。
「『アアルの羽根』には有効となる作用に『主』も『副』もないのだなあ」
「副作用のない薬剤はあり得ないと、薬学部の一回生でも習うことだぜ」
「言い方が悪かったなあ。少し説明を急ぎすぎたか。どんな作用が出ても、それは人を死に至らしめる。それが『アアルの羽根』という薬剤の効能なのだ」
僕は疑いの目で見ていたが、それはあくまで安生から情報を聞き出すための芝居だった。相手が食いつけばさらに話を聞けるだろう。
話が分からないというふりをして、どんどん相手にしゃべらせてしまおう。
しかし、そんな駆け引きは無用だとすぐに分かった。安生は相手が話についてきているかを気にしているように振舞っていたが、きっとそれは最低限の説明さえすればあとは分からなくても仕方がないという考え方であったらしく、話はさらに先へと進められたからだ。
「この白の塊は実は一つ一つが細かな糸のような物質でできているのです。それが『羽根』と名付けられた由縁でしてなあ。その微細な糸を吸い込めば、たちまちその人物の呼吸器から血管へと染み入って心臓の働きを止めてしまう……言わば心臓麻痺を引き起こすのですなあ」
まるで薬学部の学校の教授が、教科書に出ている物質を実際に調達して説明しているかのようだった。
しかし、いくら丁寧に説明されても、「アアルの羽根」の効能は信じがたい。
それにもしもこの薬剤で鳩中の父親らが殺されたというのなら、彼らの体内から何らかの毒物反応が検知されるはずだ。
それとも、実は薬物による犯行の疑いがあるのだが、それを警察もマスコミも隠しているとでも言うのだろうか。
「『アアルの羽根』はそうして心臓に作用した後、血液に混じって体内に残る。残りはするが、徐々に血液と同じ物質へと変容を重ね、最終的には投与された者と同化するのだ。分解と吸収の速度はアルコールの数千倍。死後三十分以内に検視を……しかも全身の血を抜いて検査しなければ、兆候さえ掴めぬだろうなあ。そういう薬剤なのだよなあ」
何と殺人に都合のいい薬剤だろうか。
僕は呆れるようにため息をつく。
安生の言うことは確かに信じがたいのではあるが、反論できずにいた。きっと恐れていたのだろう。「信じられないのなら、その身で味わってみるか」と言われて、小瓶の中身を投与されることを。
きっとそれくらいはしてくるだろう。
何せ、いきなり自分がこの事件の犯人だと自白し、そしてこれから目の前の人間を殺害すると述べた人物なのだ。
どれだけ相手が狂っているのかは分からないが、正気を期待することこそまさにこの状況では「狂っている」だろう。
しかし、わざわざこうして自分の犯行を話して、そのトリックも明かしたのはどういう訳なのだろうか。
そこに僕が疑いを向けると、安生は話を先に進めるのだった。
「この薬剤があれば、犯罪の証拠は残りません。少なくともこの場であなた方を殺害しても、それもまた心不全と判断されるだけですなあ。おおよそ、他殺を疑うのが関の山でしょう。しかし、その方法も犯人も分からない」
そう安生が言うと、隣に座っていた鳩中の膝が震え始めるのが見えた。
安生がここに来たのは「鳩中を殺害するため」と話していたのを思い出す。しかし、本当にそうなのだろうか。僕は一つ深呼吸をした。
「ただこいつを殺すつもりならとっくにやってる。それに、前の二人のように誰にも明かさないまま殺害すれば、犯行文通りになる。それをあんたはあえて崩そうとしている。それはどうしてなんだ」
僕の質問に、安生は嬉しそうに笑ったようだった。
犯行文の通りに殺害を進めるのは予告殺人の醍醐味であろう。ちょうどそれは、予告状を出して盗みを行う怪盗のようだ。
練りこんだストーリーに沿って事件を完遂することは、犯罪者の醍醐味のように思われた。少なくとも僕はそう考えた。
それがふいになる可能性があるのに、どうして安生はにこやかなのだろうか。
「そこで鳩中さん。取引をいたしませんかな?」
安生は胸ポケットに再び小瓶をしまうと、今度は代わりに内ポケットから数枚の書類を取り出すのだった。僕らの方へと向けられて差し出された。
そこには「遺言状」というタイトルで始まる文章と、それに添えられるようにして「確認書」と印刷された紙が置かれる。
僕と鳩中は顔を揃えてまずは「遺言状」に目を通してみた。
文面によると、それは鳩中ハヤタの名で作られた遺言状となっており、心臓発作の持病があったこと、そしていつ死ぬとも分からない自分の身を考えてこの遺言状を残すと書かれている。
「父が心臓に病を抱えていたことは、残念ですが聞かされていませんでしたね。本当ですかね」
言葉は静かだが、震える声の節々に怒りが感じられる。
続きを読んでみると、僕も唸ってしまうような内容になっていた。
遺言では鳩中ハヤタは過去の過ちを悔いて、安生に家を含む全財産を譲り、研究結果やその他の知的財産も残さず彼に差し出すと書かれている。
「どうですかなあ。ゆっくり考えてみて下さいね」
「こんな偽装された遺言が有効になるはずない。赤の他人であるあんたに全ての財産が渡る……。筋が通らないにも程があるぞ。そっちこそ熟考が必要だな」
「筋を通すための、『確認書』だ。法律の世界では不自然さや不明確さよりも、何よりも、事実が優先されるのだなあ。だからこそ、その『確認書』に鳩中さんのサインが欲しい。そうすればたちまちその遺言状の内容は本物となり、この私に莫大な財産が移るというわけだよ」
「それが為されなければ、鳩中を殺して犯行文通りになると」
「アアルの羽根は楽園への道しるべ」
喉の奥で愉快そうに笑う声が聞こえた。
僕の胸の中にはもちろんこの卑劣な行為への憤りはあったのだが、それ以上に軽蔑の感情が強く刻まれた。最後の最後で自分の利益に走った彼は、自信に満ちてこの家を訪問した時の姿とは似ても似つかぬように感じる。
こいつは小悪党だ。根っからの悪党でもなければ、覚悟を定めた悪人でもない。
僕はこんな中途半端な悪に屈することはないと思って、鳩中に向けて首を振るのだった。
「おやおや、さらに罪を重ねたいと。そうなれば鳩中さんは裁きを受けねばなりませんなあ」
「その怪しげな薬剤も現物を抑えられれば証拠になる。つまり、あんたも警察に引き渡されれば終わりだぞ」
「ともすれば、そうかもしれませんなあ。しかし、焦っては良くないですな。それでは一体、どのような疑いで警察は私を拘束するというのですかな」
問われてすぐに「何だそんな簡単なことを」と思ったのだが、いざ口にしようとするとためらってしまう。
安生をどう通報すればいいのか。
今なら住居不法侵入で警察を呼べば捕まえられる。脅迫でも良いだろう。しかし、それは警察が来るまでに相手に立ち去られては、証拠も残らないし、「アアルへの羽根」で脅されていることを話してもあくまで「疑い」でしかないので、警察も本気では動いてはくれまい。
それにここでの交渉決裂……安生を手ぶらで帰してしまうことは、鳩中や僕に命の危険さえ及ぶことだ。
考えを巡らせて他の可能性を探っていると、押し黙っていた鳩中が切り出した。怯えが極度に達して声が上気しているように聞こえる。
「父を殺した容疑者」
放たれたその言葉は僕にとっては盲点を突かれたようで、自然に頷いてしまった。
鳩中の怒りの込められた言葉で、僕は一つのことに気づく。彼女が目の前にしているのは、肉親の命を奪った憎っくき相手なのだと。
「ふむ、悪くないですなあ。それではその証拠が揃えてあると仰るのですなあ」
そう指摘されるとたちまち鳩中は黙ってしまう。相手を糾弾しようという勢いが沈んでいくのを僕は感じていた。
僕らにはまだ彼が確実に鳩中ハヤタ氏を殺害したという証拠を掴んではいないのだ。
追い討ちをかけるようにさらに安生は述べる。
「疑わしいのならば問い合わせてみるのがよろしいと思いますが、私はね、つい数日前まで警察で拘留されていたのですよ。鳩中ハヤタ氏が亡くなった時も、それを知ったのは東京の留置所でした」
そう述べると彼はポケットから一枚の紙片を取り出した。
「どうぞ、差し上げますので好きなだけお調べになったらよろしいですよ」
渡された紙に目を通すと、それは「私物返却書」と書かれており、物品がリストアップされていた。
鍵束、書籍、携帯電話と書かれている。おそらくこれは安生が留置所から解放される時に返却された私物の一覧なのだろう。日付も入っている。三月の一日から十八日。この紙が本物か偽物かを調べれば彼が三月一日から十八日まで警察に身柄を拘束されていたことが分かる。
つまり、これは彼のアリバイなのだ。
鳩中ハヤタ氏が殺害されたのは三月の四日なので、その間、安生は警察署にいたことになる。
警察が証人になった、最強のアリバイだ。
これで事実上、安生が鳩中ハヤタ氏を殺害するのは無理ということになる。
安生を追い詰める術を失った鳩中は、意気消沈といった風で肩を落としていた。睨みつけるように眺めていた留置所の私物返却書が偽物であるように念じているようだった。
残念ながらそれはないだろう。
僕は一旦頭の中を静かにして考える。
安生はここまで立派な悪人をやっておきながら、ここ一番、最後の最後でせせこましい要求に出るという小悪党だ。
しかし、彼がどういう人物であろうと、鳩中の父親を殺害したという事件においてはアリバイがあるので無実なのだ。
それならば誰が鳩中ハヤタ氏を殺害したのか……?
それに先ほど安生は自分が鳩中を殺害した犯人だと自白していなかったか。
僕が顎に指をやって考えている間、まるでそれに張り合うようにして安生は髭を撫でていた。
自白の真偽はともかく、安生は鳩中ハヤタ氏の殺害に絡んでいるようだ。そうでなければあそこまで堂々と犯行文を見せられるはずもない。
袋小路にあるこの状況で困っていると、安生は前触れもなく立ち上がった。
「三日、差し上げます。私は犯罪者ではありますが、せっかちではありませんのでなあ。春が終わる頃までに全てが片付いていれば気持ちが良いと、そう思っているだけなのですなあ」
「三日後にまた来るのか」
「左様。ですが、あくまで会いに来るのは鳩中さんです。あなたには微塵も用事はありませんのでな。それではくれぐれも、体調を崩されませんように。春は気温も変わりやすいのでなあ」
そう告げると、安生は鳩中の顔だけを見てから出て行ってしまった。誰の見送りも受けず、迷うことなく出口へと向かって、ゆったりと玄関で靴を履くとそのまま去る。
安生の姿が見えなくなって、僕は気が抜けてしまった。
突然の訪問者と電撃的な告白。
そして、まさに青天の霹靂とも言える「脅迫」を目の当たりにして、僕は安生の背中が見えなくなった外の景色を玄関から眺めていた。
リビングに戻ると、鳩中は泣いていた。
この家の財産全てを譲らなければ殺す。そう言われたのだから動揺するのもしょうがない。僕は彼女の正面に立って言葉を発する。
「心配は要らない。あの悪党の尻尾は必ず捕まえてみせる。何を考えてるか知らないが、ああいうやつを野放しにしておいたらいけねえんだ」
心の底から彼女を心配して放った言葉のはずだった。
しかし、鳩中はいつまでも泣き止まず、僕から顔を背けようとしていた。
そこで無理にでも正面に回ってさらに元気づけようとしたのだが、ついには僕は鳩中に突き飛ばされてしまう。
無抵抗に体は崩れ落ちるようにして後方に飛び、ソファーに叩きつけられる形で僕は座ってしまった。
「あなたは結局、謎解きがしたいだけなんですか。それならもう私からは離れた方がいいです」
「このままあいつに……あいつの好きなようにさせて良いのかよ」
涙ながらの鳩中の言葉に僕は戸惑ってしまった。しどろもどろになって反論をしていた。
何を言われているのか分からなかった。
僕はただあの安生という悪党を捕まえるために頑張ろうと言っただけだ。それはつまり鳩中を助けたいという気持ちから来たものだし、謎解きがしたいだけなんていう批判は心外だった。
「父が亡くなったんですよ。私には母も居ませんし、その他の家族も居ないんです。だから、それだけ父に頼って、父と力を合わせて生きてきました。そんな存在が居なくなって……もう何が何だか分からないのに、あなたやあの安生とかいうおじいさんが話を勝手に進めて、てんやわんや……もう、少し静かにさせてほしいものです。少し、放っておいて下さい」
喚くような鳩中の口ぶりに僕はつい頭に血が上ってしまった。
僕は鳩中のために事件を解決しようとしてきた。それは彼女を助けたいからと言う気持ちに突き動かされていたからで、その他の衝動はない。
それなのに、まるで僕が彼女を不快にさせたような言い方は間違っている。
「だったら、どうして僕を毎日家に上げてるんだよ。追い返せば良かっただろ」
「それは」
鳩中は口ごもって何も言わなくなってしまう。
そうか。彼女は父を失って腑抜けのようになってしまっていた。そこに僕がやって来て食事やら選択やらをし始めたのだ。要は便利な人間が来たと思ってたんだな。
すっかり逆上してしまった僕は机を叩くと、そのまま安生と同じように玄関から外に出て行ってしまった。
そこまで言うのなら一人になったらいい。一人にさせてやる。
僕は行くあてもなくただ鳩中の家から姿を消すことにする。
鳩中と言い争いをしてからすっかりこの事件について興味が無くなってしまったかというと、そうではない。
一人で家に居る時も気がつけばスマホに届いた例のメールを読み返してしまっていた。
どうしてここまでこの事件が気になるのだろう。
理由ははっきりとしないが、僕はこの「アアルの羽根」に関する一連の事件について、何かに取り憑かれたかのように真相を知りたくなっていた。
それは例え鳩中に「謎解きがしたいだけ」と指摘されても、気持ちは変わることがない。
「けれど、ただ謎が解ければ良いってものでもないんだ。きっとそれじゃ満たされない」
僕はそう呟きながらテレビをつけてワイドショーを眺めていた。
一体、あの安生という老人はどうやって鳩中の父親を殺害したのか。
実は帰宅してからずっと頭の中を占めているのはその疑問ばかりで、鳩中に別れ際に浴びせられた言葉や、三日後に再び現れるという安生のことは頭の隅に追いやられている。
僕はどこか人間的な欠陥があるのかも知れない。
誰かが悲しんでいる時に一緒になって悲しめない。誰かが怒っている時に、手放しでそれに共感できない。そんなことは何度もあった。
今回だってそうじゃないだろうか。
僕も幼い頃に事故で両親を亡くし、その後は親戚に育てられたのだが、そのことから肉親を失うことが特別な体験だとは思っていない節があったのかもしれない。
しかし、それにしても、いや、だからこそ、僕は鳩中の気持ちに寄り添ってあげなければならなかったのではないだろうか。
鳩中は精神が不安定になってテレビばかり観て来客にも敏感になっていて、そのことにまるで心を配れないでいたのだ。
その間、やっていたことと言えば鳩中ハヤタ氏の書斎を探ることばかりだ。
しかも何一つとして成果は得られなかった。
僕は垂れ流されているワイドショーから芹沢雅の名前が出てくるのを聞いた。
そう言えば、この第二の被害者にはまだ何も着手していなかった。
その事を思い出して、僕はスマホを取り出すと送られてきていた犯行文に再び目を通した。
「メンカラーは星の森への散策を計画するうちに罪を暴かれる」
安生が明かした所によればこのメンカラーというのが、第二の被害者である芹沢のはずだ。となると、この「星の森への散策を計画する」というのが死の直前の状況なのか。
そんな推理を組み立てるうちに僕はじっとしていられなくなった。
芹沢雅を殺害したのも安生だとしたら、何か証拠が残っているかもしれない。それを見つけ出せば安生の犯行を証明できるのではないだろうか。
それから僕はとある医科大学にやって来ていた。
芹沢雅という人物についてインターネットで調べると、勤務先の情報はすぐに出てきていた。と言っても、誰かがリークしているとか、そういう噂が広まっているとか、不確実な情報ではない。
日本科学振興会の公式ページに情報が載っていたのだ。
芹沢雅は医科大学の研究員として勤めていたらしい。その研究は鳩中ハヤタ氏と同じく人工肺の研究だ。この医科大学で研究を続けながら、日本科学振興会の会員としての活動もしていたと言う訳だ。
大学の入口にはマスコミがたむろしていて、守衛が彼らを通さないようにしていた。学生は皆、学生証を提示して入構しているようであった。僕は自分の大学の学生証を見せて事情を説明した。もちろん嘘をついたのだ。この大学の図書館に用事があり、勉学のために使用させて欲しいと。
僕は他大学の間でこうして図書館の相互利用が出来る制度があるのを、事前に確かめていた。
呆気にとられたような顔をしていた守衛は、電話でどこかに確認をとっていたが、やがて戻ってきて渋々といった様子で僕を通してくれた。
あとは芹沢雅の研究室を探して調査をするだけだ。
警察がいれば厄介なことになるが、僕は鳩中の家に出入りしていた時に知ったのだ。事件の被害者とは言え、その場が殺人現場にでもなっていなければ、ほとんどその場所の警戒は周囲の人物に任せられているということを。
警察もそこまで人員を割いていられないという訳だ。
ホームページで芹沢の学部も把握していたので潜入はスムーズにいった。
問題は研究室の鍵がかかっていた場合だったが、そのケースでの対応も考えていた。どこかで火をおこしたり警報器を鳴らして気を引くか、警察に不審者の情報を流して職員達を動揺させればいい。その隙に鍵を探すのだ。
しかし、何とも不用心なことに部屋の鍵は開いていたので、僕はあらかじめ考えていた策は取らずに済んだ。
研究室に入るとほとんどの物品は警察に押収されてしまったらしく、パソコンも書類もほとんどが残っていない状況だった。
これでは確かにあまり用心しても仕方がないのかもしれない。
僕はスマホの犯行文をもう一度読み返す。
今のところ、手がかりはこれだけだ。
本棚を眺めていると、僕はある違和感に気がついた。呼吸器や循環器の専門書に混じって、そこには見慣れない書物が収められていたからだ。
「古代エジプトのファラオたち その業績と生涯について」
アアルの羽根といい、犯行文と言い、この事件にはやけにエジプトに絡む事柄が多いな。
そう何気なく思っただけだった。
僕はせっかくならと犯行文に出てきた三人のファラオについて調べてみることにした。
ラネブ、メンカラー、ネチェルカラー。
その三名ともファラオとして記録に残っているだけであり、彼らが何を行ったのかは今のところ不明なのだという。
しかし、ネチェルカラーだけには目を引く記述があった。
「ネチェルカラーは様々な研究から、ニトクリス女王と同一視されるのが一般的である……?」
そうなると、ネチェルカラーは男性ではなくて女性だ。
それはつまり犯行文の中で殺害予告がされているのは鳩中ハヤタと芹沢雅と鳩中史恵ということになる。ファラオの組み合わせを考えても男、男、女、と辻褄が合っている。
やはりこの犯行文は秀逸だ。
己の世界観に従って悪を成す。これこそが僕の理想とする悪のようだった。しかし、あれを書いたのは小悪党の安生である。
どこか悔しさを感じながらファラオの本を元に戻そうとした時だった。
僕の頭には安生のあるセリフが蘇っていた。
ちょっと……待てよ。
あいつは、あの時、そう、この文の解説の時に何て言った? 僕の聞き違いだったのかも知れないが、もしそうでないとしたら、安生の言動には一つ不審な点が残ることになる。
もし、僕の推理が正しいものだとしたら……この事件は全く違った形を見せることになるだろう。
安生は僕にあの時、閃きを得ることが必要だと述べた。
そして今、僕の得た「閃き」はもしかしたら安生の本当の悪事を暴くものになるかもしれないのだ。
僕が芹沢雅の元で手に入れた「閃き」。
それを元にこれから調査を進めれば、もしかしたら安生の鼻を明かせるかもしれない。
安生が僕に述べていた言葉の中に、辻褄の合わない部分がある。
それについてを明らかにすれば事件の隠れていた本質に至れるかもしれない。
後編に続く